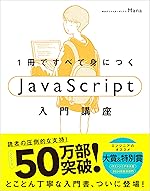-
-
睡眠中に脳内の老廃物が洗い流されるシステムが研究で明らかになってきています。
しかし、睡眠薬がその「脳の掃除」を妨げている可能性があるとのことです。
睡眠の質と脳の健康に関する重要な情報です。
-
-
-
AIを使い始めた筆者が、その面白さと便利さに夢中になっている様子が語られています。
AIによって作業効率が向上する一方で、情報過多による疲労感も感じているようです。
AIとの付き合いを通じて、自身の変化や社会への影響についても考察しています。
-
-
-
PostgreSQLのSQLインジェクションの脆弱性が9年以上放置されていました。
この脆弱性がアメリカ財務省への侵入に利用されました。
GIGAZINEがこの件について詳しく解説しています。
-
-
-
TypeScriptコンパイラがGo言語に移植され、コンパイル速度が10倍向上する予定です。
移植は既存のTypeScriptコードを忠実に再現するアプローチで行われ、型チェックの互換性が重視されています。
Compiler APIの代替手段やパフォーマンス向上の要因など、TypeScript利用者への影響についても解説されています。
-
-
-
この記事では、SaaS全盛期において大企業が中小企業に比べて恩恵を受けにくい現状を指摘しています。
大企業がSaaS導入に二の足を踏む理由として、特殊な業務要件やPM人材の不足を挙げています。
大企業が競争力を維持するためには、差別化要因の明確化、SaaSを前提とした業務改革、DX人材の育成が重要であると説いています。
-
-
-
電話詐欺が多発し、知らない番号からの電話に出ない人が増えています。
その結果、通常の連絡手段としての電話の役割が低下しています。
Togetterでのまとめ記事として、この問題が取り上げられています。
-
-
-
個人開発で月5万円(理論値)のサービスを作ったノウハウが公開されています。
集客やマネタイズ、SEO対策、UI/UX改善など、個人開発に役立つ情報が満載です。
Udemy講座のアフィリエイトで収益を上げている方法や、AIを活用したレビュー分析についても解説されています。
-
-
-
Pixel標準アプリのレコーダーが優秀で、録音しながら文字起こしが可能です。
2タップで録音と文字起こしが開始でき、操作もシンプルで使いやすいです。
Googleドキュメントとの連携や、テキストベースでの検索機能も便利です。
-
-
-
画像編集ソフトGIMPの7年ぶりの大規模アップデート版がリリースされました。
GUIライブラリがGTK 3へアップグレードされ、HiDPIスクリーンでのUIスケーリングが大幅に改善されています。
非破壊フィルターの導入により、フィルターのON/OFF操作が気軽に行えるようになりました。
-
-
-
フリーの画像編集ソフトGIMPの最新版となる「GIMP 3.0」がリリースされました。
約7年ぶりの大型アップデートで、GUIライブラリのアップグレードやHiDPI環境におけるUIスケーリングの改善などが図られています。
非破壊フィルタの導入やsRGBを超える色空間のサポートなど、多くの変更や改良が加えられています。
-
-
-
文系非エンジニアの記者がコーディングエージェントを活用して自分用アプリを開発した事例を紹介しています。
AIエージェント「Cursor」と「Claude 3.7 Sonnet」を組み合わせることで、テキストエディタを1時間半程度で作成できたとのことです。
しかし、セキュリティリスクや情シス部門の負担増などの懸念点も指摘しており、安易なAIツールの利用に警鐘を鳴らしています。
-
-
-
この記事では、AI駆動開発における「Project as Code(PaC)」の重要性を解説しています。
PaCとは、システム開発プロジェクトの全てをコード管理・バージョン管理する取り組みです。
AIに正しいコンテキストを伝えるために、プロジェクト情報を網羅的に管理することが重要と述べています。
-
-
-
この記事では、NTTコミュニケーションズが提供するテキスト・会話安全性判定サービス「chakoshi」について紹介されています。
chakoshiの特徴やユースケース、課題について解説されています。
特に、会話コンテンツの安全性確認における課題や、今後の発展に期待する点が述べられています。
-
-
-
複雑なフォームと状態管理についてのプレゼンテーション資料です。
Speaker Deckに掲載されています。
スライドの内容はクリエイターに帰属します。
-
-
-
この記事は、AIエンジニアDevinを活用してCIパイプラインを改善した事例を紹介しています。
Devinに具体的な指示を与えることで、CIの実行時間を半分に短縮することに成功しました。
AIエージェントとの協働は今後の開発組織にとって重要なテーマになると述べています。
-
-
-
あるユーザーがBluetooth接続のモニタとキーボードを希望した。
しかし、エンジニアがBluetoothを技術要件と誤解釈した。
その結果、プロジェクトが炎上する事態となった話です。
-
-
-
YewはRustのWebアプリケーションフレームワークで、WebAssemblyを使用します。
Yew公式サイトの日本語対応が進み、Nextバージョンでは日本語ドキュメントが充実しています。
環境構築からチュートリアルまで、Yewを使ったWebアプリケーション開発の手順が解説されています。
-
-
-
WizがGoogle Cloudに買収されることになりました。
規制当局の審査を経て、WizはGoogle Cloudに加わります。
クラウドセキュリティをより簡単に、よりアクセスしやすく、よりインテリジェントにすることを目指します。
-
-
-
OpenAIがAgents SDKというAIエージェント作成ツールを発表しました。
この記事ではAgents SDKのクイックスタートを日本語のコメント付きで丁寧に解説します。
Agentのタスク割り振りや不適切な入力の検知、Web検索機能などを確認できます。
-
-
-
ソースネクストから光ディスクの状態を診断し、データをバックアップできるライティングソフト「B's Recorder GOLD 21」が発売されました。
新機能として、ディスクの劣化判定や救出機能が搭載されており、大切なデータが失われる前に移行作業が可能です。
劣化したディスクからデータを強制的にコピーして保存できる「修復バックアップ」機能も搭載されています。
-
-
-
この記事は、少人数チームがセキュリティ監査を効率的に乗り越えるためにSaaSツールVantaを導入した事例を紹介しています。
Vantaの導入により、自動テスト機能での要件チェック、ポリシー整備の効率化、充実したサポート体制、監査機関との連携が円滑に進みました。
結果として、SOC2認証取得プロジェクトをスムーズに進め、厳格なセキュリティ基準をクリアできたことを述べています。
-
-
-
AIを使ったレポート作成において学生の間に差が出ているという話題。
自分の疑問を明確にしてAIに問う学生と、課題をそのままAIに問う学生がいるとのこと。
この差がレポートの質に現れるのではないかという考察が述べられています。
-
-
-
ファーストリテイリングが不正アクセスを受けたと発表しました。
取引先や従業員の個人情報漏えいの可能性があるとのことです。
ユニクロとジーユーの顧客情報は含まれていません。
-
-
-
AIコードエディター「Cursor」は開発者コミュニティで急速に支持を広げています。
この記事では、プログラミング知識がない人でも使えるCursorの基本と文章作成での活用法を紹介します。
CursorはChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデルを統合し、文章作成やコーディングをAIがサポートします。
-
-
-
GitHub Actionsの外部ActionでVersionTagを使っているものをCommitHashに一括変換する方法を紹介。
サプライチェーン攻撃対策として、外部ActionをCommitHashで指定し、RenovateやDependabotで管理する。
ツールactionspinを使うことで、複数のリポジトリで一括変換が可能。
-
-
-
この記事では、CursorとFigma MCP Serverを連携させて、FigmaのデザインデータからUIコードを自動生成する方法を紹介しています。
FigmaのAPIキーを取得し、CursorのMCP設定を行うことで、CursorのAgent機能からFigmaのURLを指定してコード生成が可能になります。
デザインシステムや共通コンポーネントがある場合は、.cursor/rulesに記述することで、より精度の高いコード生成が期待できます。
-
-
-
キャディでのApache Icebergの活用事例を紹介する記事です。
製造業におけるデータ活用の難しさや、データレイクハウスのアーキテクチャについて解説しています。
キャディがIcebergをどのように活用し、今後の課題について述べています。
-
-
-
Java 24が正式にリリースされました。
HotSpot JVMやガベージコレクションの改善により性能が向上しています。
32ビット版Windowsのサポートが削除された点も注目です。
-
-
-
東京大学のレポート課題でChatGPTの使用が許可された。
ただし、使用したプロンプトは全て参考文献として記述する必要があるという。
このルールは、学生の理解度をより本質的に評価できる可能性がある。
-
-
-
Serverless Frameworkのv3からv4への移行について解説されています。
v4ではライセンス変更やNode.jsのサポート状況、TypeScriptのネイティブサポートなど多くの変更点があります。
移行の理由やGitHub Actionsでの動作方法についても詳しく説明されています。
-
-
-
Rubyのデバッグ技と推奨事項をまとめた記事です。
VS CodeのRuby LSP拡張やlaunch.json設定の変更など、効率的なデバッグ方法が紹介されています。
debug.gemとIRBの統合や、特定のコマンド繰り返し実行など、便利な機能も解説されています。
-
-
-
Dolby Atmosのライブ配信技術に関する記事です。
KORGのLive ExtremeがDolby Atmosのリアルタイム配信を実現し、東京・春・音楽祭で初のライブ配信が行われました。
筆者はその配信を体験し、まるでホールの客席にいるかのような臨場感に感動した様子が綴られています。
-
-
-
RAGの検索性能を低下させるテキストの特性について解説されています。
Embeddingの性能は文章の位置、単語、量に影響されるとのことです。
対策として、文章分割や言い換えなどを検討する必要があるようです。
-
-
-
タネンバウムの『コンピュータネットワーク』はネットワーク技術の解説書です。
理論だけでなく歴史的経緯や政治的背景も解説し、技術への理解を深めます。
技術者や学生だけでなく、ネットワークに興味がある人にもおすすめです。
-
-
-
デジタル庁の平将明大臣は、マイナ免許証交付開始に合わせ、海外での運転には従来の免許証との2枚持ちを推奨しています。
マイナ免許証は住所変更のワンストップサービスやオンライン講習などの利点がある一方、海外では利用できません。
小売店のセルフレジでの年齢確認実証実験も行われ、スマホでのスムーズな年齢確認が確認されました。
-
-
-
この記事では、マネーフォワードの社内AIツール開発者が生成AIの活用法を紹介しています。
プログラミングにおけるコード補完や技術調査、企画書作成、会議の要約などにAIを活用しています。
特に、Cursorとの適切な距離感を保ちながら、AIと人間が協力してコードを書くことを意識している点が重要です。
-
-
-
Google AI Studioの新機能、Gemini 2.0 Flash Experimentalを使うと、画像から簡単に横顔や後ろ姿を生成できます。
服装や髪型の変更も容易で、アニメ調の画像にも対応しています。
プロンプトがうまくいかない場合は、英語で試したり、簡単な指示から始めるのがおすすめです。
-
-
-
この記事は、エンジニアリングマネージャーとして、チームを活性化させるための著者の考えをまとめたものです。
良いと思ったことを共有し、感謝する風土を作ることで、メンバーが気持ちよく働ける環境を作ることを意識しています。
互いに敬意を持ち、Aliveなチーム、Aliveな組織に近づくことを目指しています。
-
-
-
この記事では、AIを活用して上司のフィードバックを再現し、そのメリットを解説しています。
AIによるフィードバックは、待ち時間の削減、遠慮のない指摘、質の均一化に貢献します。
具体的なプロンプト例や、組織におけるAI環境の整備の重要性も紹介されています。
-
-
-
この海外記事では、米国のクラウドサービスから移行する理由と、その方法について解説されています。
プライバシーと政治的な理由から、USクラウドへの依存を減らすことが重要になっています。
Microsoft 365、Bitwarden、GitHubなどの代替サービスへの移行経験が紹介されています。
-
-
-
SesameAILabsが開発した対話型音声生成モデル(CSM)のリポジトリです。
このリポジトリでは、モデルのコードやドキュメントが公開されています。
対話型音声生成に興味がある開発者や研究者にとって役立つ情報源となるでしょう。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より