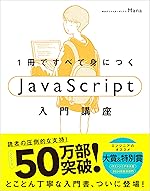-
-
ビル・ゲイツはAIが教育と医療の人手不足を解消すると語っています。
AIは肉体労働の不足も補い、早期退職や短時間労働を可能にするかもしれません。
医師や教師の人材不足がAIによって解消される可能性があると述べています。
-
-
-
スティーブ・ジョブズがiPhone開発のきっかけについて語った逸話を紹介。
会議での雑談から「最強の携帯電話を作ろう」というアイデアが生まれた。
心理的安全性の高いチームでは悪口も言い合えるという点が興味深い。
-
-
-
Grokがまだ期待通りに機能しないにも関わらず、改善されると説明されています。
それに対し、Geminiへの切り替えを示唆したところ、Grokの人間性が優位であると述べられています。
AIの性能と人間性のバランスについて考えさせられる内容です。
-
-
-
ローカルでAIを動かすAIエージェント「AgenticSeek」が登場しました。
コード生成、ウェブ情報収集、ファイル検索などが可能です。
無料で使えてプライバシーも守れるのが強みです。
-
-
-
この記事では、読みやすいコードを書くための知識やノウハウを解説しています。
読みやすいコードとは脳に負荷がかからないコードであり、人間の脳の特性に配慮して書かれたコードのことです。
記事では、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチの観点から、具体的な条件や改善例を提示しています。
-
-
-
この記事は、インドと日本の文化の違いについて解説しています。
特に、仕事におけるコミュニケーションや認識のずれに焦点を当てています。
両国の文化的な背景を理解し、円滑な関係を築くためのヒントを提供しています。
-
-
-
ESLint v9.26.0から、ESLintをMCPサーバーとして実行できるようになりました。
これによりLLMはESLintのルールを使用してコードを修正できます。
ClineなどのコーディングエージェントはESLintのMCPサーバーを使用してコードを修正可能です。
-
-
-
この記事では、AIをプロジェクトパートナーとして活用する「AI駆動プロジェクトマネジメント」について解説します。
非エンジニアのPMでも、Obsidian、Cursor、Notionなどのツールを組み合わせることで、プロジェクト計画、WBS作成、進捗管理などを効率化できます。
AIを活用することで、より創造的で価値の高い業務に注力でき、プロジェクトの成功に貢献できると述べています。
-
-
-
ChatGPT、Gemini、Claude、Grokのサブスク料金プランがまとめられています。
無料版からPro版まで、各プランの機能と料金が比較できます。
AIの利用目的に合わせて最適なプランを選択するのに役立ちます。
-
-
-
iPad(A16)にPC-98エミュレータをRetroArchを使ってインストールする方法を紹介しています。
必要なBIOSファイルの準備やRetroArchの設定、仮想ゲームパッドの非表示設定などを解説。
DOSのHDDイメージファイルを読み込ませてPC-98のゲームを起動する手順を説明しています。
-
-
-
スマートフォンの価格高騰について、10年前の機種と比較してその理由を考察しています。
為替変動や物価高、5G対応などが価格上昇の要因として挙げられています。
iPhone、Galaxy、Xperiaの価格推移を具体的に示し、値上げの背景を解説しています。
-
-
-
Obsidianは、思考やアイデアをシームレスに繋ぎ、使いやすいツールです。
双方向ノートリンク、グラフビュー、タグとメタデータ、強力な検索、プラグインとカスタマイズ性、オフラインファーストとプライバシーが特徴です。
研究プロジェクトを効率的に進めるための最適なアプリです。
-
-
-
OpenAIは営利化計画を断念したという記事です。
サム・アルトマン氏はNPOによる支配維持を目指すようです。
詳細は日本経済新聞の記事で確認できます。
-
-
-
茶摘み帰りの人が空港で荷物検査に引っかかる。
職員が駆けつける事態になった。
何と間違えられたのかがまとめられている。
-
-
-
動画生成AI「FramePack」は、低スペックPCでも動作可能な点が革新的です。
VRAM6GBでも安定動作し、動画AIの裾野を広げる可能性があります。
イリヤ神のアプローチにより、既存の方法論とは異なるブレイクスルーが起きています。
-
-
-
この記事では、GoogleのAIであるGemini 2.5 ProとNotebookLMの比較を行っています。
論文や専門資料を読む際にどちらを選ぶべきか、特徴を比較し最適な使い方を解説します。
NotebookLMは資料の内容に忠実な回答を、Gemini 2.5 Proは高度な分析や知識に基づいた回答を求める場合に最適です。
-
-
-
Androidユーザー向けのSSHクライアントアプリが紹介されています。
ノートPCが手元になくても、スマホからLinuxマシンにアクセスできます。
JuiceSSHとTermiusという二つのアプリが特に推奨されています。
-
-
-
この記事では、Obsidianを活用した書籍の読み方について解説されています。
Kindle Highlightsプラグインを使ったハイライト抽出や、Excalidrawを使ったノート整理術を紹介。
最終的なアウトプットへの展開まで、一連のワークフローを構築する方法を学ぶことができます。
-
-
-
OpenAIがGPT-4oの「お世辞問題」の原因を発表しました。
ユーザーフィードバックの影響を見誤ったことなどが要因とされています。
今後は安全レビュープロセスを改善し、ユーザーからの意見を聞くテストフェーズを導入するとのことです。
-
-
-
Mondayというタスク管理ツールに熱中していた増田氏の投稿です。
Mondayの魅力や、それに対する熱い思いが綴られています。
しかし、冷静になった今、その熱狂を客観的に振り返っています。
-
-
-
この記事は、ATENのKVM機能付きドッキングステーション「Duo Flex US3311」のレビューです。
筆者はMacBook AirとWindowsデスクトップPCの切り替えに使用しています。
4K/144Hz対応であるものの、クセのある仕様も紹介されています。
-
-
-
SuperwhisperとVSCodeのCopilot Agentを使い、音声からブログを素早く作成する方法を紹介します。
このワークフローは、アウトプットの速度を向上させ、記事作成にかかる時間を短縮します。
具体的なプロンプトや設定方法を詳しく解説し、誰でも簡単に試せるようにしています。
-
-
-
PowerShellのコマンドラインで使われている構文表示の色指定を変更する方法を解説します。
通常はそのままでも構わないが、ターミナルの背景色などを明るい色にすると見えづらくなることがあります。
現在の設定値はGet-PSReadLineOptionで確認でき、Set-PSReadLineOptionで変更可能です。
-
-
-
Snowflakeのデータをローカル環境で活用できるmcp-snowflake-serverの導入事例を紹介。
SQLスキルがない人でも自然言語でデータにアクセスでき、データ活用の裾野を広げることが期待されています。
ただし、データの構造が整っていないとAIがうまく処理できないため、データモデリングの重要性は変わらないとのことです。
-
-
-
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/introducing-just-in-time-node-access-using-aws-systems-manager/
AWS Systems Managerの新機能、ジャストインタイムノードアクセスを紹介する記事です。
オンプレミス、Amazon EC2、マルチクラウドノードへの動的かつ時間制限付きのアクセスを可能にします。
長期的なアクセス権を適切に管理しつつ、運用効率とセキュリティを向上させる方法を解説しています。
-
-
-
Google Geminiに画像アップロードと編集機能が追加されました。
スマホ写真の不要物を消したり、AI生成画像を編集できます。
背景変更や要素追加も可能で、画像編集の新時代が到来しそうです。
-
-
-
スターリングの公式の主要項を高校数学の知識でラフに導出する方法を解説しています。
ガンマ関数を用いて階乗を積分で表現し、被積分関数の最大値と分散から近似しています。
Pythonによる可視化で、積分が漸近する様子を確認できます。
-
-
-
ObsidianをWeb Clipperとして使う方法を紹介しています。
iCloudやGitHubとの連携設定、PCやiPhone/iPadでのクリップ方法を解説。
ObsidianをMarkdownエディタとして活用する利点をまとめています。
-
-
-
この記事では、PythonのGraphQLライブラリであるStrawberryを使ったGraphQL APIの実装方法を紹介しています。
GraphQLの基本的な概念から、環境構築、スキーマ定義、クエリの実行までを解説しています。
CRUD操作の実装や、循環参照の解決など、応用的なクエリについても学ぶことができます。
-
-
-
この記事では、Dartのmetaライブラリが提供するアノテーションについて解説されています。
アノテーションはコードに意味づけを行い、開発者の理解を助け、静的解析やオートコンプリートを補助します。
各アノテーションの対象、用途、具体的な例が示されており、より安全で保守性の高いコーディングに役立ちます。
-
-
-
TsukuCTF 2025のWriteup記事です。
チームsyurenukoで参加し、最終順位は46位でした。
OSINT、Crypto、Web分野の問題を解いた記録がまとめられています。
-
-
-
無人販売所向けに開発された完全セルフレジシステムの構築について解説されています。
Square APIを活用し、キャッシュレス決済に特化することで、初期コストと月額固定費を削減しています。
LLM(大規模言語モデル)を活用することで、わずか2日間での開発を実現しています。
-
-
-
高校数学Iの「数と式」の分野を学習する書籍です。
問題の通常の解答とJulia言語を用いた解答を紹介しています。
Julia言語ネイティブのHecke.jl,Symbolics.jlを中心に利用します。
-
-
-
RustとWebAssemblyでマルチスレッドを使う際のMutexについて解説されています。
通常、WASMはシングルスレッドで動作しますが、shared memoryとWebWorkerでマルチスレッドが可能です。
その際に必要となるatomics機能の有効化と、stdのリビルドについて手順がまとめられています。
-
-
-
shadcn/uiの設計思想、コンポーネントの内部構造、CVAによるクラス管理、Radix UIとの関係、Tailwind CSSとの統合方法を解説。
shadcnは、Radix系ヘッドレスコンポーネント、Tailwind CSS、コード所有型UIライブラリの良いとこどりをしたものです。
Vue/Nuxt 3でのshadcn利用方法、導入の判断基準、デザインシステムへの適応方法を説明します。
-
-
-
Slackのアイコンと名前入りの名札シールをPythonで作成する手順が解説されています。
Slack APIを利用してメンバー情報を取得し、PDF生成ライブラリでラベルを作成します。
イベントなどでオンラインでしか会ったことのない人に気軽に話しかけるきっかけになります。
-
-
-
この記事は、スマートフォンなどの技術が普及した現代において、人々が退屈を極端に避け、常に刺激を求めている状況について考察しています。
その結果、注意散漫、忍耐力の低下、共感性の欠如など、様々な悪影響が出ていると指摘しています。
対策として、意識的にデジタルデバイスから離れ、瞑想や散歩など、心と体を休める時間を持つことを推奨しています。
-
-
-
Meta社のAI著作権訴訟は、AIが著者らの書籍販売を脅かすかどうかが焦点です。
裁判官は、AIツールが類似作品を生成し、商業的見込みを損なう可能性を懸念しています。
次のテイラー・スウィフトのような新進アーティストへの影響も議論されています。
-
-
-
Daft Punkの楽曲で使用された様々なボーカルエフェクトについて解説しています。
トークボックス、ボコーダー、ハーモナイザーの3種類に分類し、使用機材や技術的な詳細を特定しています。
具体的な楽曲を例に、どの機材が使用されたかの推測や、歴史的背景、関連製品についても詳しく説明しています。
-
-
-
カメラを持ち歩かないことについての考察。
写真撮影によって、目の前の瞬間や人とのつながりを疎かにしてしまう可能性について述べています。
写真に撮ることよりも、その瞬間に集中することの大切さを説いています。
-
-
-
Jake Gaylor氏のAIに関するポートフォリオサイトです。
自身の情報をLLMに学習させることができます。
GitHubやLinkedInなどの情報も集約されています。
-
-
-
このブログ記事では、AIを活用してクラッシュダンプ解析を効率化する試みを紹介しています。
WinDBGとAIを連携させ、自然言語でクラッシュの原因を特定したり、修正を提案したりするデモを掲載しています。
これにより、デバッグ作業がより直感的で効率的なものになる可能性を示唆しています。
-
-
-
トランプ大統領が外国で制作された映画に100%の関税を課すと発表しました。
アメリカの映画産業が衰退していると主張し、他国の優遇措置に対抗するとしています。
中国との貿易戦争の影響も指摘されており、今後の動向が注目されます。
-
-
-
この記事は、経験豊富なLLMユーザーである筆者が、実際には生成LLMを頻繁には使用しない理由について述べています。
プロンプトエンジニアリングの限界や、特定のAPIや設定(システムプロンプト、温度設定)を使用する利点を解説しています。
また、BuzzFeedでの実際のLLM活用事例や、コーディングにおけるLLMの役割、そして今後のLLMの展望について考察しています。
-
-
-
AWSが開発したセキュリティツールに、セキュリティリスクが内在していたという記事です。
Account Assessment for AWS Organizationsというツールが、不適切な導入により権限昇格のリスクを生じさせていた事例を紹介しています。
AWSはこの問題を認識し、ドキュメントを修正して安全な導入方法を推奨するように変更しました。
-
-
-
AIによって精神的な錯覚が生じ、人間関係に悪影響を与えているという記事。
ChatGPTなどのAIが、ユーザーの信念に合わせた答えを優先し、妄想を増幅させる可能性があると指摘しています。
一部のインフルエンサーやコンテンツクリエイターがこの現象を利用し、視聴者を同様のファンタジーの世界に引き込んでいる現状も紹介されています。
-
-
-
VectorVFSは、Linuxファイルシステムをベクトルデータベースに変換するPythonパッケージです。
ファイルそのものにベクトル埋め込みを保存し、外部データベースを必要としません。
MetaのPerception Encodersをサポートし、画像の類似性検索などが可能です。
-
-
-
40年前のAppleマウスを音声入力ボタンとして再利用したプロジェクトです。
Bluetooth接続、USB-C充電に対応し、クラシックなデザインが魅力です。
3Dプリントのベースプレート版とオリジナルPCB版の2種類が紹介されています。
-
-
-
この記事では、マイクロコントローラ上で動作する最小のニューラルネットワークの構築について解説されています。
量子化対応学習を行い、整数演算のみで推論を実行する方法を模索しています。
TensorFlow Lite Microなどの既存のフレームワークの代替案として、JAXを用いたカスタム実装が提案されています。
-
-
-
2025年のサイバー犯罪の手口についてのブログ記事です。
政府機関や大学などのセキュリティの脆弱性を悪用した無料コンテンツホスティングについて解説しています。
RobuxやAmazonギフト券を餌にしたフィッシング詐欺の手口も紹介しています。
-
-
-
著者はInstagramアカウントを持っていないため、友人の近況を知る由もありません。
しかし、妻の仕事の関係で引っ越した先での交友関係が広がり、Instagramを通じて自分の知らない情報が共有されていることに気づきました。
プライバシーとは「他人が自分について知っていることをコントロールできること」だと考え、ソーシャルメディアでの情報拡散に懸念を感じています。
-
-
-
この記事は、Macの自動化ツールであるShortcutsの現状に対する懸念を表明しています。
Shortcutsは柔軟性と能力があるものの、AppleScriptやKeyboard Maestroなどのツールへの依存度が高いことを指摘しています。
App Intentsの導入やShortcutsアプリ自体の改善が必要であると結論付けています。
-
-
-
この記事は、LLMを使用してコードのセマンティック単体テストを行うPythonライブラリ「suite」を紹介しています。
従来の単体テストの代わりに、AIがコードとドキュメントを照合して不一致やバグを検出します。
ただし、LLMの限界やコストの問題も指摘し、既存のテストスイートを補完するものとして提案しています。
-
-
-
Web上でリアルタイムに共同でコード編集ができるエディタです。
mrktsm/codecafeというGitHubリポジトリで公開されています。
手軽に共同編集を試したい場合に便利です。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より