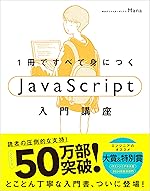-
-
CursorにPMBOKやDMBOKをインストールして専門業務を加速化する未来について書かれています。
Cursorに専門知識を叩き込むことで、一貫性のある知識ベース、学習コストの削減、ミス防止、ドキュメント作成の効率化などが期待できます。
PMBOKやDMBOKを例に、具体的なCursorとの組み合わせ方やアプローチ案が紹介されています。
-
-
-
この記事では、ObsidianとCursorという2つのツールを組み合わせ、情報管理と知的アウトプットを向上させる方法を解説します。
Obsidianは知識のネットワーク構築に強く、CursorはAIによる文章生成と整理に強みがあります。
2つのツールを組み合わせることで、情報収集からアウトプットまで効率的なワークフローを構築できます。
-
-
-
LLMを活用するために、あらゆるコンテンツからMarkdownに変換して一箇所に集める方法を紹介しています。
GitHubを使い、コンテンツごとにリポジトリを分け、git submoduleで管理する基本方針を解説しています。
はてなブログ、Zenn、Notion、TwitterなどのデータをMarkdownに変換する具体的な方法を説明しています。
-
-
-
UUIDを短くするライブラリuuid58が作成されました。
UUIDをBase58でエンコードすることで、URLに埋め込んでもスッキリしたIDに変換できます。
Web標準のAPIに依存し、エラー処理やパフォーマンス、tree-shakingなどにも配慮されています。
-
-
-
数十人規模のチームが自律性を発揮するための試みを紹介しています。
時間管理の重要性と、チームの自主性を高めるための工夫が述べられています。
Speaker Deckで公開されているプレゼンテーション資料です。
-
-
-
Docker Desktopの新機能、Docker MCP Toolkitを使うとMCPツールが簡単に利用できます。
この記事ではMCPクライアントにClineを用いてDocker MCP Toolkitを利用する方法を解説しています。
Docker Desktopがあれば、スムーズにMCPサーバを利用できます。
-
-
-
DockerのMCP Toolkitは、コンテナ化されたMCPサーバーをAIエージェントと統合するDocker Desktopの拡張機能です。
従来、ローカルでMCPサーバーを実行するには、JavaScriptやPythonのパッケージ管理ツールを使用する必要がありました。
DockerのMCP Toolkitを使用すると、信頼されたDocker MCPカタログからMCPツールを簡単にインストールできます。
-
-
-
インターネット時代、AI時代における「質問」の重要性を説く記事。
「調べたらわかる」「聞けばわかる」という考え方は、質問を軽視していると指摘しています。
正しい質問をすることは非常に難しく、知的行動であると述べています。
-
-
-
Claude 3.7のシステムプロンプト流出について、その解説とAI開発者や利用者への示唆をまとめた記事です。
システムプロンプトの基本概念から、流出の概要、重要ポイント、セキュリティと倫理的影響について解説します。
AI開発者やプロンプトエンジニア、一般ユーザーがこの事象から何を学ぶべきかについて考察します。
-
-
-
この記事では、MarkdownエディタObsidianのおすすめプラグインが紹介されています。
日々の記録、コードスニペット管理、ブログの下書きなど、様々な用途で役立つプラグインが紹介されています。
プラグインの活用でObsidianを自分好みにカスタマイズし、作業効率を向上させることができます。
-
-
-
Science Tokyoのデザインシステムに関するWebスタイルガイドです。
Webサイト管理者や運用担当者など、Webサイトに関わるすべての方が利用できます。
デザイントークン、コンポーネント、ページパターン、デザインリソースなどが定義されています。
-
-
-
オーディオ業界の再編が進んでいます。
サムスン電子傘下のHARMANがSound Unitedを買収しました。
オーディオ産業全体の再編がさらに進むきっかけになる可能性があります。
-
-
-
GIGAZINEの記事では、自分の歯を培養してインプラントや詰め物の代わりにする技術を紹介しています。
この技術は、歯の再生医療における新たな可能性を示すものです。
失った歯の代替として、患者自身の細胞を利用できる未来が期待されます。
-
-
-
この記事では、GoogleのAIツール「NotebookLM」について解説しています。
iPadからNotebookLMを使う方法や、その特徴を紹介しています。
特に、資料を読み込ませて要約するのが容易なUIについて詳しく説明しています。
-
-
-
iPad Pro (M4)と周辺機器を購入した記録です。
6年ぶりにiPad Proを新調し、1TBモデルを選択。
Magic Keyboardは重いが、使い心地は良好とのこと。
-
-
-
この記事では、外部仕様書の確認をSlackワークフローに組み込み、Devinにサポートしてもらう試みを紹介しています。
外部仕様書のレビューは、開発初期段階での認識の相違を防ぎ、品質向上とリリース後の不具合減少に繋がります。
DevinをSlackワークフローに統合することで、開発プロセス全体の効率化と高品質化を目指しています。
-
-
-
このサイトは、商業サイトと個人サイトが共存したウェブ黎明期(1993年~2003年)の歴史をまとめたものです。
JUNET、WIDEプロジェクト、Mosaic、Netscapeなどの技術やサービスが登場し、個人ニュースサイトや日記サイトが隆盛しました。
阪神淡路大震災、Windows95発売、テレホーダイ開始、2ちゃんねる開設など、社会現象も記録されています。
-
-
-
font-sizeにremを使うべきかについての記事です。
Chromeの文字拡大機能をサポートするためにremを使用するか、pxを使用するかの判断基準について述べられています。
検証コストを考慮し、状況に応じて使い分けることを推奨しています。
-
-
-
この記事は、AIコーディングツールCursorの入門記事です。
VScodeユーザーがCursorへ移行する際のポイントを解説しています。
AIにコーディングさせ、ブラウザで動くシューティングゲームを作成する手順を紹介します。
-
-
-
CursorのBackground Agentは、リモート環境で非同期に動作するエージェントです。
複雑なタスクをオフロードし、ユーザーは他の作業を続けられます。
バグ修正や機能開発、リファクタリングなどに適しています。
-
-
-
GitHub - marcboeker/gmail-to-sqlite: Index your Gmail account to a SQLite DB and play with the data.
GmailのデータをSQLiteデータベースにインデックス化するツールです。
これにより、Gmailのデータをより柔軟に分析できます。
GitHubリポジトリで公開されており、MITライセンスで利用可能です。
-
-
-
この記事では、TypeScriptの型レベルプログラミングと高度な設計手法について解説します。
条件付き型や型演算、型レベルプログラミングによる設計改善などを紹介します。
また、パフォーマンス最適化や開発体験向上のためのテクニックも解説します。
-
-
-
iPhoneユーザーが仕事用のスマホを探しているならPixelがおすすめです。
PixelはGoogle系サービスとの相性が良く、カスタマイズ性も高いです。
Geminiを活用した情報収集や最新AI機能も魅力で、二刀流でそれぞれの強みを活かせます。
-
-
-
品質保証(QA)の技術に焦点を当てたプレゼンテーション資料です。
品質とデリバリーを両立させるためのアプローチを紹介しています。
試行錯誤の過程で得られた知見が共有されています。
-
-
-
この記事は、クロスファンクショナルチームになるための壁を崩すためのお作法について解説しています。
一度に多くのことを行うのではなく、ステップを分割して学習効率を向上させる方法を提案しています。
コーチングの例を参考に、チーム学習を促進するアプローチを紹介しています。
-
-
-
CastingONEの大沼氏による、分割代入時のショートハンドを強制するESLintルールの作成に関する記事です。
カスタムルールの作成手順から、ESLintへの設定、テストまでを詳細に解説しています。
TypeScriptでESLintカスタムルールを導入し、コードの可読性を向上させる方法を学べます。
-
-
-
この記事では、Cursorエディタで使用される`.mdc`ファイルについて解説しています。
`.mdc`ファイルは、AIアシスタントが参照するプロジェクト固有のルールを定義するファイルです。
従来のカスタムルールと比較して、より柔軟で構造化された管理が可能になります。
-
-
-
Reactの内部構造、特にレンダーとコミットのプロセスについて解説しています。
イベント「Matsuriba vol.9」での発表資料です。
Reactの動作を効率的に理解するための情報がまとめられています。
-
-
-
Google VidsにAI動画生成機能が追加されました。
Veo 2を使用し、プロンプトを入力するだけでカスタムビデオクリップを生成できます。
現在は英語のみ対応の機能もありますが、様々なGoogle Workspaceプランで利用可能です。
-
-
-
この記事では、AIエージェントが相互に通信、連携、タスク委譲するための3つのプロトコル、A2A、MCP、ACPについて解説します。
A2Aは異なるシステム間でエージェントが連携するための標準、MCPはエージェントが外部データやツールにアクセスするためのプロトコルです。
ACPはローカル環境でのエージェント間通信に特化しており、低遅延でプライバシーが重要な場合に適しています。
-
-
-
この記事では、WebAssembly(Wasm)とTypeScriptのパフォーマンスを比較検証しています。
大規模データ処理に焦点を当て、ソート、AVL木、グラフアルゴリズムを実装し性能を比較しています。
結果として、WasmはTypeScriptに比べ平均2倍の速度向上とメモリ使用量の削減が確認されました。
-
-
-
Neovimの最新機能extuiで、コマンドラインがよりスマートになります。
コマンドラインのシンタックスハイライトやecho表示位置の変更などが可能です。
:messageのフローティングウィンドウ化で出力のコピーも容易になりました。
-
-
-
Next.js 14.2.28 から 15.3.1 へのバージョンアップ対応について解説されています。
codemodを利用した自動更新や手動修正が必要な箇所、MUIやSentryの更新についてまとめられています。
Turbopackのサポート状況やSentryの設定変更など、具体的な手順が記載されています。
-
-
-
この記事では、StorybookのparametersをTypeScriptで型安全に扱う方法を紹介します。
module augmentationとdeclaration mergingを活用し、parametersの型を拡張します。
MSWやStorycapなどの外部パッケージの型定義を追加する例や、自前のdecoratorからparametersを参照する例も解説します。
-
-
-
この記事は、勾配ブースティング決定木(GBDT)の理論をゼロから解説しています。
勾配降下法、ブースティング、決定木という3つの要素を組み合わせて構成されており、実務やデータ分析コンペで人気があります。
XGBoost、LightGBM、CatBoostといった代表的なライブラリの比較も行い、それぞれの特徴や使い分けについて解説します。
-
-
-
この記事では、研究者がSlackに代わるコミュニケーションツールとしてMatrix + Elementを導入するメリットを紹介しています。
Matrixは分散型チャットプロトコルであり、異なる大学や組織に所属する研究者間のコラボレーションを円滑にします。
セキュリティ、チャット履歴の保存、ファイル共有など、研究活動に役立つ機能が豊富に備わっています。
-
-
-
この記事では、dotfilesの構成と管理方法について紹介されています。
dotfilesを整備することで、環境構築の効率化、設定の一元管理、ツールの見直しができます。
具体的なツールとその選定理由、転職後の環境構築で役立ったことについても解説されています。
-
-
-
この記事では、ビジネス書を読むことが時間の無駄である理由を解説しています。
ビジネス書は感情的な訴求に偏り、稀な成功事例を普遍的な戦略として語ることが多いと指摘しています。
著者は、現実に基づいた意思決定、状況に応じた戦略、実践的な知識の重要性を強調しています。
-
-
-
Lightricks社による画期的な13BパラメータのAIモデルです。
前例のないスピードと品質で動画作成に革命をもたらします。
高度なマルチスケールレンダリング技術により、競合モデルより30倍高速です。
-
-
-
半導体回路のシミュレーターです。
ブラウザ上でインタラクティブに回路を描画し、電磁場を可視化できます。
金属、半導体、誘電体など、さまざまな材料を扱えます。
-
-
-
この記事は、LLMがエージェントとして世界とインタラクトするための標準APIであるMCPを批判的に考察しています。
HTTPトランスポートにおけるSSEとStreamable HTTPの設計上の問題点を指摘し、WebSocketへの代替を提案しています。
また、IBMのACPやGoogleのA2Aといった関連プロトコルの必要性についても疑問を呈し、業界全体の方向性に警鐘を鳴らしています。
-
-
-
日本の民間月着陸船が月の周回軌道に入りました。
6月に着陸を試みる予定です。
SpaceXで打ち上げられたResilienceランダーには、月の土を採取するミニローバーが搭載されています。
-
-
-
Bonfire 1.0のリリースに向け、これまでの道のりを振り返り、今後の方向性を示す記事です。
「ゆっくりとしたソフトウェア」というアプローチで、長期的な回復力と有意義な参加を重視しています。
技術がケアなしに拡大した場合の損害を考慮し、異なる展望を提案しています。
-
-
-
Chromiumのバグを利用して、特定のJavaScriptコードでheadless Chromiumブラウザをクラッシュさせることができるという記事です。
この手法はボット検出に使える可能性があるものの、ユーザー体験を損なう、影響が大きいなどの理由から、本番環境での利用は推奨されていません。
より良いボット検出は、静かで影響が少なく、状況に応じた判断ができるものであるべきだと結論付けています。
-
-
-
PlainBudgetは、シンプルなテキストベースの予算管理アプリです。
ブログ記事では、このアプリについて詳しく解説されています。
macOS版のベータ版は有料ですが、CLI版は無料かつオープンソースです。
-
-
-
React Three Fiberを中心としたエコシステムを紹介するWebサイトです。
3DコンテンツをReactで開発するための情報がまとめられています。
サンプルやドキュメントも充実しています。
-
-
-
子供の数学学習にノートを使うことを推奨する記事です。
過去のノートを見返すことで成長を実感でき、学習の記録にもなります。
ノートを「Math Machine」と名付けるなど、楽しく取り組む工夫も紹介されています。
-
-
-
小説家がビデオゲームのライターに、そしてその逆も増えているという記事。
ゲーム業界の不安定な状況と、小説家としての収入の不安定さが背景にある。
ゲームと小説、それぞれの執筆形態の違いや文化的な位置づけについても触れられている。
-
-
-
Chromeは、Android版で不要な通知に対する警告機能を導入しました。
この機能は、デバイス上の機械学習を使用して、詐欺やスパムの可能性のある通知を検出し警告します。
通知の内容が詐欺やスパムの可能性がある場合、サイト名の警告メッセージが表示され、サイトの登録解除オプションが表示されます。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より