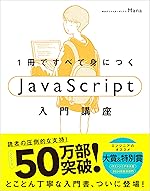-
-
この記事は、ソフトウェアエンジニアがホンダに転職して感じた4つのことについて述べています。
ソフトウェアに関する経験を持つ人が少ないこと、開発インフラが整っていないことなどが挙げられています。
一方で、能力の高い人が多いことや、労働組合の存在意義についても触れられています。
-
-
-
東大などが国会議員の過去の発言をAIで分析し、政治的立場をまとめたサイト「KOKKAI DOC」を発表しました。
議員の国会での発言から政治的立場を数値化し、視覚的に表現することで、有権者が選挙時に情報に基づいた判断をしやすくすることを目指しています。
各議員の発言が整理され閲覧でき、発言から分析された政治的立場をグラフで可視化し、政党や議員の立場を直感的に知ることができます。
-
-
-
和田卓人氏による技術選定に関するプレゼンテーション資料です。
2025年版として、技術の進化の方向性を示唆しています。
Speaker Deckで公開されています。
-
-
-
神名データベースは、國學院大學 古典文化学事業によるものです。
古事記に登場する神々の情報を網羅的に提供しています。
神名、神格、系譜などの詳細な情報を検索・閲覧できます。
-
-
-
MicrosoftがVBScriptの非推奨フェイズ移行に伴い、検出方法を案内しています。
VBScriptはシステムの自動化に活用されていましたが、PowerShellやJavaScriptに取って代わられています。
VBScriptの依存関係を見直し、システム全体で.vbsファイルをスキャンすることが推奨されています。
-
-
-
マイクロソフトがWindowsでMCPをサポートすると発表しました。
AIエージェントがWindowsやアプリと連携可能になります。
ファイルシステムやウィンドウ管理がMCPサーバとしてアクセス可能になるようです。
-
-
-
業務中のイヤホン利用に関する話題です。
ミーティングに耳だけ参加という状況も許容されているようです。
会社の柔軟な働き方について触れられています。
-
-
-
この記事では、AIエージェントの進化とともに登場した「MCP(Model Context Protocol)」について解説されています。
MCPはAIモデルが外部のデータソースやツールと連携するためのオープンな標準プロトコルです。
MCPはAIアプリケーションのためのUSB-Cポートのようなものであり、AIエージェントの可能性を大きく広げる鍵となる技術です。
-
-
-
GitHub Copilot Coding Agentが発表されました。
IssueをAIにアサインすると、自律的にプログラミングを行います。
GitHubの開発ワークフローを支援する新機能です。
-
-
-
この記事では、メーカー勤務者がPythonを学ぶ意義について解説されています。
日々の業務で発生する、外注するほどではないが面倒な作業を自動化できる点が強調されています。
周囲からの感謝や信頼を得られ、課題発掘から実装までの一連の経験を積むことができると述べられています。
-
-
-
日本の半導体新設工場に関する記事です。
7つの工場が建設されたものの、過半数が稼働していません。
AI向けの先端製品を製造できていない状況を伝えています。
-
-
-
AIの回答を根拠にした「国鉄の車両にゴミが溢れている昔の新聞写真」の捏造疑惑について検証した記事。
話題となった朝日新聞フォトアーカイブのツイート写真をもとに、記事の真偽を確かめています。
実際の新聞記事を確認し、検証結果をまとめています。
-
-
-
Windows Subsystem for Linux(WSL)がオープンソースとして公開されました。
これにより、WSLのソースコードがGitHubで入手可能になり、コミュニティによる開発参加が可能になります。
WSLのアーキテクチャや各コンポーネントに関する情報も提供されています。
-
-
-
東映アニメーションが2025年3月期決算説明資料を訂正しました。
当初「わんだふるぷりきゅあ!」にAI技術を活用していると記載していましたが、誤解を招く表現だったとしています。
実際にはAIの活用実績はないとのことです。
-
-
-
AI時代の認可制御入門について解説されています。
「AI でつくる人」「AI をつくる人」のための実践的なガイドです。
認可制御の基礎から、AIに関連する技術を活用する際に注意すべき観点まで詳しく説明されています。
-
-
-
マイクロソフトがWindows Subsystem for Linux (WSL) のコードをオープンソースとしてGitHubに公開しました。
これにより、ユーザーは自身でコードをビルドしたり、独自のカスタマイズが可能になります。
WSLは、Windows上でLinux環境を用いたアプリケーション開発やテストを手軽に行えるようにします。
-
-
-
AIブームの実態について考察した記事です。
AIでなくても良いところにAIが使われ、チャットインターフェースがAIと認識されている現状を指摘しています。
冷静に技術の本質を見極めることの重要性を説いています。
-
-
-
MicrosoftはMicrosoft 365 Copilotに対して、ユーザーが追加学習を行える新機能「Microsoft 365 Copilot Tuning」を発表しました。
これにより、法律事務所が契約書をCopilotに追加学習させ、自社の形式や専門知識を備えた契約書のドラフトを生成できるようになります。
Copilot Tuningは、Microsoft 365 Copilotライセンスを5000以上保有する顧客を対象に提供開始予定です。
-
-
-
この記事では、バックアップとDRを計画する際に意識すべきことをまとめています。
バックアップやDRの目的設定から、障害シナリオごとのRTO/RPO/RLOの定義、リストアやDR発動の基準定義など、計画フェーズで重要な要素を解説しています。
設計・実装フェーズでは、バックアップ手法の実現性確認やデータ整合性の確保、ネットワーク帯域の調査など、具体的な実装に関する注意点を説明しています。
-
-
-
死の間際の脳波を分析した研究を紹介しています。
心停止に至る過程でガンマ波活動が増加することが判明しました。
この脳波パターンが臨死体験の走馬灯現象と関連する可能性が示唆されています。
-
-
-
AIの出現により、エンジニア不足の感覚が薄れたという記事です。
AIを前提とした開発、例えばTailwind CSSやDDD、クリーンアーキテクチャの採用が進んでいます。
AIを使えないエンジニアは、挨拶ができないのと同じという意見も述べられています。
-
-
-
AWS認定全冠を達成した筆者が、その経験をもとにAWS認定の価値を多角的に考察しています。
AWS認定の概要から、取得の意義、全冠までの道のり、得られたスキルや変化を詳細に解説します。
AWS認定が個人のスキルアップだけでなく、組織全体のイノベーションと生産性向上につながることを示唆しています。
-
-
-
NVIDIAがプロプライエタリだったインターコネクト「NVLink」を他社にも限定公開する「NVLink Fusion」を発表しました。
NVLink Fusionの採用にはNVIDIA CPUまたはGPUとの組み合わせが必須です。
この動きは、AMDやIntelが提唱するオープンな規格「UALink」への対抗策と見られています。
-
-
-
事業会社でのマルウェア解析環境構築とフィッシングメール解析の結果を紹介しています。
マルウェア解析環境を構築するメリットや必要なスキル、環境構築の設定方針と準備したものを解説。
実際にフィッシングメールの検体を解析し、攻撃者の意図や手口を解説しています。
-
-
-
九州大学の研究グループが、三毛猫の毛色を決める遺伝子を特定しました。
60年間謎だったオレンジ遺伝子の正体は「ARHGAP36遺伝子」であることが判明。
この遺伝子の不活性化がオレンジ/黒の斑の形成に関与することが明らかになりました。
-
-
-
DDR5で64GBメモリーが1枚で実現し、PCの最大搭載容量が256GBに到達しました。
Crucialから登場したDDR5-5600 UDIMM 64GBモデルは、大容量メモリーのメリットを検証します。
メモリーの基本やデュアルチャネル、枚数による速度の違いなどを解説し、速度低下の影響を検証します。
-
-
-
VS CodeがオープンソースのAIエディタになることを発表しました。
GitHub Copilot Chat extensionのコードをMITライセンスで公開し、VS Codeのコアに組み込む予定です。
AI開発における透明性の向上とコミュニティの貢献を促進することを目指しています。
-
-
-
東映アニメーションの決算資料で、アニメ「わんだふるぷりきゅあ!」の制作にAIが活用されていたことが明らかになりました。
色の指定や色塗りミスの自動修正、動画中割の生成など、さまざまな作業の効率化を図っているとのことです。
ただし、後に東映アニメーションは決算資料を一部訂正し、実際にはAI技術を利用していないと発表しました。
-
-
-
ドリームアーツの飯野氏が、自社製品SmartDBの操作をMCPに対応させる実験を紹介しています。
Clineを用いることでMCPサーバーの実装コードを10行程度に抑え、OpenAPIから自動生成を試みました。
Cline利用時の工夫点として、サンプルコードの用意、こまめなgit commit、タスク分割などを挙げています。
-
-
-
DevinのCoreプランを個人で1ヶ月使ってみた感想がまとめられています。
Coreプランは個人利用の範囲であれば十分で、費用対効果も高いとのことです。
思った通りにコードを書いてもらうには、Issueの整備が不可欠だと述べています。
-
-
-
Rustの精密キャプチャ `use<...>` について解説しています。
抽象戻り型におけるジェネリック引数のキャプチャについて、問題点と解決策を提示。
`use<...>` 構文による精密キャプチャで、不要なキャプチャを削減する方法を紹介します。
-
-
-
C#と.NETでのオブジェクト指向プログラミングを基礎から学べる書籍です。
SOLID原則や設計パターンを実践的に身につけたいエンジニアにもおすすめです。
業務開発や設計における本質的な理解を目指します。
-
-
-
この記事では、Tiptap v3 betaで`editor.isActive`が動かない問題について解説します。
原因は、エディターのtransactionの度に再レンダリングしなくなった変更によるものです。
解決策として、TiptapのイベントをフックしてsetStateする方法を紹介しています。
-
-
-
Pythonを使って航空機のフライト制御の基礎を体験する記事です。
PID制御を組み合わせたウェイポイント追従シミュレーションを実装します。
AI技術を活用した高度なフライト制御の可能性についても解説します。
-
-
-
GitHub Actionsを1年使って得た知見がまとめられています。
前段ワークフローの成功・スキップ時の実行や、過去のワークフローのアーティファクト取得など、実践的なテクニックが紹介されています。
AIを活用したShell芸や、共通ワークフローの作成、手動実行での動作確認など、効率的な開発に役立つ情報が満載です。
-
-
-
Webサイトの言語設定をIPアドレスの地理情報に基づいて行うのはやめるべきだと筆者は述べています。
VPNの使用や多言語国家のユーザーを考慮すると、IPアドレスからの言語推測は不正確です。
Accept-Languageヘッダーを読み取り、ユーザーの言語設定を尊重すべきと主張しています。
-
-
-
Zod 4が安定版としてリリースされました。
パフォーマンスが向上し、バンドルサイズが削減されています。
新しいAPIや機能が多数追加され、開発効率が向上しています。
-
-
-
この記事は、19世紀のフランスの写真家ナダールの人物写真を紹介しています。
アレクサンドル・デュマ、ヴィクトル・ユーゴー、サラ・ベルナールなど、著名な人物のポートレートを通じて、彼の才能と時代を捉えています。
写真を通じて、歴史上の人物の個性や息吹を感じることができるでしょう。
-
-
-
このページでは、2009年以降に著者が作成したサイドプロジェクトがまとめられています。
売却されたもの、現在もオンラインのもの、そして静かに消えていったものもあります。
WordPress、Laravel、Reactなど、様々な技術スタックが使用されています。
-
-
-
欧州投資銀行(EIB)は、ヨーロッパの技術セクターに700億ユーロを投資します。
アメリカとのイノベーションギャップを埋め、AIなどの新興技術分野を強化することが目的です。
この投資は、民間投資を呼び込み、最大2500億ユーロの資金を動員する可能性があります。
-
-
-
リモートのソフトウェアエンジニアの求人情報がまとめられています。
アメリカ国内での高給な仕事に特化しています。
マイクロソフト、Airbnb、Coinbaseなど有名企業の情報も掲載されています。
-
-
-
KDE Plasma向けの新しい仮想マシンマネージャー「Karton」が開発中です。
Qt QuickとKirigamiで構築され、libvirt APIを使用します。
Google Summer of Code 2025のプロジェクトとして開発が進められています。
-
-
-
clawPDFは、エンタープライズソリューションにあるような機能を備えた仮想PDFプリンターです。
PDF/AやPDF/Xなど様々な形式でドキュメントを作成でき、メタデータの削除やパスワード保護も可能です。
スクリプトインターフェースによる自動化や、ネットワークプリンターとしての利用もサポートしています。
-
-
-
goboscriptは、テキストベースでScratchプロジェクトを作成できる言語です。
テキストエディタで記述し、gitなどのバージョン管理システムも利用可能です。
高度なマクロシステムや、ローカル変数などの追加機能も備えています。
-
-
-
Brian Kitano氏のブログ記事で、Llamaをスクラッチから実装する方法を紹介しています。
論文を理解し、段階的にモデルを構築するアプローチを解説しています。
RMSNorm、RoPE、SwiGLUといったLlama特有の要素を実装し、改善していく過程を詳細に説明しています。
-
-
-
Procolored社のプリンターにマルウェアが混入していたことが判明しました。
同社は当初、誤検出として問題を軽視していましたが、セキュリティ企業の調査によりマルウェアの存在が確認されました。
感染した場合は、OSの再インストールが推奨されています。
-
-
-
データベース設計の原則について解説されています。
現実世界の情報を適切に表現するためのデータベース設計の重要性が述べられています。
設計原則に従うことで、セマンティックな混乱や技術的な不安定さを回避できると主張しています。
-
-
-
Windowsに新しいコマンドラインテキストエディタEditが登場しました。
EditはオープンソースでGitHubからインストール可能です。
軽量でマウス操作、複数ファイル編集、検索・置換、ワードラップなどの機能を備えています。
-
-
-
Go言語で効率を上げるために、間接参照のレイヤーを調べています。
io.Readerインターフェースをbytes.Readerとして扱うことでコピーを省略したいと考えています。
bufio.Readerが内部のリーダーを公開していないため、unsafeパッケージを使ってハックしています。
-
-
-
この記事では、ゲーム開発者が直面するシェーダーコンパイルの複雑さを解説しています。
異なるプラットフォームやAPI間でのシェーダーの互換性維持の難しさを説明しています。
著者はSDLへのGPU API提案の背景と、その設計における技術的・政治的課題を議論しています。
-
-
-
Diffusionモデルについてわかりやすく解説されています。
Transformerベースの言語モデルとの違いについても説明されています。
画像生成AIの仕組みを理解するのに役立つでしょう。
-
-
-
この記事では、現代人が無意識のうちにテクノロジー、特にスマートフォンやアルゴリズムに対して宗教的な態度をとっていると指摘しています。
いいねやシェアの数、ミームへの参加などを通して、集団の一員であるという感覚を得て、それをテクノロジーへの崇拝と混同していると述べています。
著者は、この現象自体は必ずしも悪いものではないとしつつも、その背後にあるメカニズムを理解し、悪意のある行為者による操作から身を守ることの重要性を強調しています。
-
-
-
Kelpは、MacOS上にバイナリパッケージをインストールするためのHomebrewの代替となるツールです。
Go言語で記述されており、Homebrewでformulaが利用可能になるのを待つ必要がありません。
インストールマニフェストで複数のコンピュータを最新の状態に保てます。
-
-
-
この記事は、書籍に記載されているフォントに関する注釈について考察しています。
かつては専門家への礼儀として存在した注釈が、現代では言葉がデータとして扱われる中で、自己表現の手段として注目されていると述べています。
フォントの重要性が変化している状況を分析しています。
-
-
-
数学の終焉について考察したブログ記事です。
数学が資本主義の機械に完全に飲み込まれる未来を憂慮しています。
人間の理解への欲求と精神の向上こそが重要だと説いています。
-
-
-
法務扶助のオンラインシステムがハッキングされ、家庭内虐待被害者の詳細を含む大量の個人データが盗まれました。
2010年からのデータがダウンロードされ、200万件以上の情報が漏洩したとBBCが報じています。
住所、生年月日、国民ID番号、犯罪歴、雇用、経済データなどが含まれている可能性があります。
-
-
-
Cogitatorは、大規模言語モデル(LLM)におけるchain-of-thought(CoT)プロンプティング手法を実験するためのPythonツールキットです。
複雑なタスクでのLLMの性能を向上させるCoTプロンプティングをサポートし、モデルの推論過程を解析します。
OpenAIとOllamaをLLMプロバイダーとして利用でき、Pydanticによる構造化されたモデル出力を検証可能です。
-
-
-
過去10万年の地球の姿をWebGLでインタラクティブに可視化する試み。
海面水位、気候変動、氷床の動きなど、歴史的データに基づいた地球モデルを構築。
THREE.jsとシェーダーを使用し、ブラウザ上で動作するデモを公開。
-
-
-
sshsyncは、SSH経由で複数のリモートサーバーでシェルコマンドを実行するためのCLIツールです。
すべてのサーバーまたは特定のグループを対象にでき、システム管理者、開発者、自動化ワークフローに最適です。
ファイルのプッシュ/プル、操作履歴とロギング、ドライランモードなどの機能があります。
-
-
-
この記事は、自由な言論の歴史と、それが現代社会に与える影響について考察しています。
特に、アメリカ合衆国における言論の自由の解釈が、他の国々と大きく異なっている点を指摘しています。
また、ジョン・スチュアート・ミルの自由論が持つ限界についても議論しています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より