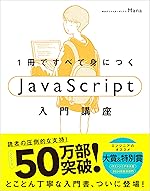-
-
DELLのサポートに関する不満が述べられています。
対応の遅さや問題解決能力の低さが指摘されています。
購入後のサポート体制に疑問を感じる内容です。
-
-
-
AIコーディングツールの利用で、開発者の生産性が19%低下するという調査結果が発表されました。
AIが生成したコードの評価、手直し、再出力に時間がかかり、効率が悪化するとのことです。
特に経験豊富な開発者が高品質なコードベースで作業する場合に、この傾向が顕著になるようです。
-
-
-
Amazonで購入したモバイルバッテリーが技適未取得製品だったという記事です。
返品が可能だったため、その手続きをレポートしています。
購入時には技適マークの確認が重要であることを伝えています。
-
-
-
このプレゼンテーションでは、AIエージェントのデータ基盤について解説されています。
データの意味と使い方を正確に理解することの重要性を強調しています。
Vertex AI RAG EngineやBigQuery Universal Catalogなどのツールを紹介しています。
-
-
-
この記事では、プロンプトエンジニアリングの重要性を解説しています。
プロンプト作成の基本的な考え方から、具体的なプロセスまでを紹介します。
生成AIを業務で活用し、効率化やスキルアップにつなげる方法を学べます。
-
-
-
AIにt_wada氏を降霊させてPRレビューをしてもらうテクニックの裏側を解説しています。
圧縮プロンプトの概念や、理論家の人名をオーガニック圧縮語として利用する仮説について考察しています。
実験結果から、人になりきってレビューをしてもらうことの効果や、プロンプト設計のポイントをまとめています。
-
-
-
SREの役割とインフラに特化したSREの戦略について解説されています。
Speaker Deckに掲載されたスライド資料です。
2025年の情報として提供されています。
-
-
-
この記事は、パスキーの仕組みと、なぜパスワードよりも安全なのかを解説しています。
パスキーは公開鍵暗号を基盤とし、秘密情報を共有せずに認証を可能にします。
パスキーの登録、認証、削除など、知っておくべきワークフローについても説明しています。
-
-
-
アナリティクスエンジニアが直面する曖昧な依頼や不確実なタスクにどう向き合い、どのような考え方でタスクを設計・遂行しているかを紹介します。
依頼の背景を丁寧に確認し、目的と要件を明確にしたうえで、実行可能な単位にタスクを分解することが重要だと述べています。
最終的に目指すのは、ユーザーが迷わずに必要な情報へたどり着き、スムーズに意思決定へとつなげられる状態をつくることだと述べています。
-
-
-
Xperia 1 VIIの販売停止の原因が、コード解析から判明しました。
SoCのコードネームが「shimanto」であることと、中国ODMのHuaqin社の定義が含まれていることが判明しました。
ハードウェア開発がHuaqin社によって行われた可能性があり、品質問題に繋がったのかもしれません。
-
-
-
この記事は、vitestでのテストにおけるbeforeEachの利用について考察しています。
beforeEachの代わりにtest contextの拡張を用いることで、テストの移植性を高め、不要なDBアクセスを削減できると提案しています。
DBつきテストの並列実行を意識した設計についても触れられています。
-
-
-
株式会社秀和システムの出版事業がトゥーヴァージンズグループに譲渡されました。
今後は「株式会社秀和システム新社」として再出発するとのことです。
長年にわたり親しまれてきた書籍を継続的に提供し、出版活動を展開していくそうです。
-
-
-
サイボウズ新人研修2025で使用されるDocker入門に関するSpeaker Deck資料です。
Dockerの基本的な概念や使い方について解説されています。
脆弱性スキャンツールTrivyを使ったDockerイメージのセキュリティチェックも紹介されています。
-
-
-
この記事は、Makefileを便利コマンドメモとして使うことに対する筆者の違和感を述べたものです。
本来はREADMEを充実させるべきであり、技術的共通認識の形成や属人化防止に役立つと主張しています。
AI Coding Agentフレンドリーな環境構築の重要性も指摘しています。
-
-
-
株式会社ヘンリーのVPoEとしての取り組みと課題についてまとめられています。
採用強化、行動指針の浸透、ミドルマネジメントの必要性を課題として挙げています。
部室長オンボーディングや採用活動、行動指針の周知などの施策を実施しています。
-
-
-
この記事は、10Xのセキュリティチームが業務委託との協働を通じて専門性を高めた事例を紹介しています。
チーム体制、課題、業務委託の選定理由、協業方法、成果、そして課題について詳細に解説されています。
特に、業務委託との連携における背景・文脈の共有、相談トピックのフォーマット化が重要であることが強調されています。
-
-
-
AI時代の設計について解説されています。
良いコードと悪いコードの例を比較。
設計の入門として役立つ情報が満載です。
-
-
-
この記事では、Microsoft Copilotを使いこなすためのポイントを紹介しています。
プロンプトスキルだけでなく、Copilotとの対話を重ねることが重要だと述べています。
ファイルの添付や会議録の活用など、具体的な活用事例も紹介されています。
-
-
-
この記事ではClaude Codeのセットアップ、Cursorとの連携、モバイルアプリ開発環境構築について解説されています。
特にiOSアプリ開発を中心に、Xcodeを使用した方法がメインで紹介されています。
Gemini CLIの導入やCursorとの連携方法、Hot Reloadの設定など、具体的な手順が記載されています。
-
-
-
この記事では、Claude Codeのhooks機能について解説しています。
hooksを使うことで、特定のアクションの前後でシェルコマンドを実行できます。
通知のカスタマイズ、自動フォーマット、ログ記録、Tool制御などが可能です。
-
-
-
この記事は、HTTPS普及に貢献したLet's Encryptの軌跡を辿っています。
SSL証明書の高コストと設定の煩雑さを解消し、無料での提供を実現しました。
ウェブの暗号化を民主化し、安全なインターネット環境の構築に大きく貢献しています。
-
-
-
米国におけるAIと著作権をめぐる議論の記録帳です。
AI学習と著作権に関する複数の裁判例や連邦著作権局の報告書をまとめています。
フェアユースの解釈や市場の希釈化など、重要な論点が浮上しています。
-
-
-
Kindle Oasisからの乗り換えにおすすめのE Ink端末としてKindle PaperwhiteとBOOX GoColor7Gen2を紹介しています。
Kindle PaperwhiteはKindleストアに特化し、高速なレスポンスが魅力です。
BOOX GoColor7Gen2はカラーE Inkとページめくりボタンを備え、複数の電子書籍ストアを利用可能です。
-
-
-
「Claude 4」を活用して、家庭用スキャナーエージェントを簡単に作成した事例を紹介しています。
スキャンした書類を家族共有のGoogle Driveに保存し、Discordで通知する仕組みを構築。
家族からの高評価を得て、スキャナーの利便性が向上したとのことです。
-
-
-
AI時代のドメイン駆動設計について解説されています。
Forkwell Library FL_100で発表されたスライド資料です。
ソフトウェア開発における設計の重要性を説いています。
-
-
-
モダンなPythonの書き方について解説されています。
mypyを使った型チェックの導入を推奨しています。
初学者やMLエンジニアにとって有益な情報です。
-
-
-
60以上のプロダクトを持つ組織における開発者体験向上の取り組みを紹介しています。
チームAPIとBackstageで構築する組織の可視化基盤について解説しています。
catalog-info.yamlやtemplate.yamlなどのTipsも紹介されています。
-
-
-
このSpeaker Deckは、SREの博士課程での研究内容を紹介しています。
ネットワークサービスの依存関係を検出するTCP/UDPソケットベースの追跡や、異種Key-Valueストアでの自動階層化を行う時系列データベースなど、高度な研究内容が示されています。
クラウドアプリケーションにおける効率的な障害 локализации のための多変量時系列データの機能削減に関する研究も含まれています。
-
-
-
AnthropicのClaude-codeをVS Code Remote Containersで利用するための開発環境設定について解説されています。
セキュリティ対策が施されたコンテナ内で、必要なツールと設定が事前インストールされています。
開発者は安全かつ迅速に開発を始めることができます。
-
-
-
Windows 11のメモ帳アプリが進化し、Markdown形式の書式設定をサポートしました。
これにより、見出しや箇条書き、URLリンクなどが簡単に表現可能になりました。
古いメモ帳アプリを使いたい場合は、設定を変更することで利用できます。
-
-
-
この記事では、AI Agentのアウトプットに『Next.jsの考え方』を反映させるプラクティスを紹介しています。
静的解析や単体テスト、リファレンス実装、AI Agentへのルール設定が重要であることを解説しています。
特に、AI Agentに『Next.jsの考え方』を都度参照させることで、実装理解度が向上すると述べています。
-
-
-
Dockerの使い方をテーマにした社内勉強会の内容をまとめた記事です。
Dockerの機能や仕組み、Webアプリケーションの実現方法を解説します。
Dockerを業務で使用する際の注意点についても触れています。
-
-
-
KARAKURI VLは日本語コンピュータユースに特化した視覚言語モデルです。
日本語環境での操作や文書理解を目指し開発されました。
Qwen2.5-VL-32B-Instructをベースに独自のデータセットで学習しています。
-
-
-
国会議事録を生成AIで要約するWebサイト「ポリ徹」が公開されました。
開発者はGoとNext.jsを使用し、半年かけて個人開発しました。
Geminiの安価モデルと構造化出力を活用し、議事録要約の精度を高めています。
-
-
-
GitHub Actionsで動作するClaude CodeからPRレビュー結果をMCPでSlackに通知する方法を紹介しています。
Slack Botの準備からGitHub Actionsのyml作成、PR作成までを解説しています。
重要な場合はメンション付き通知など、今後の発展も期待されます。
-
-
-
Go言語で自作コーディングエージェントnebulaの開発入門書です。
コーディングエージェントの動作原理を理解できます。
複数ファイル編集やPlanモード、会話記憶機能の実装を通して学べます。
-
-
-
この記事ではContext Engineeringの概要と、ClaudeCodeを使った実践例を紹介しています。
Context Engineeringとは、適切なタイミングかつ適切な形式でContextを提供するシステムを設計・構築する手法です。
AIが活躍できる仕組み作りをいかに上手く設計するかが鍵となります。
-
-
-
株式会社FLINTERSの勉強会に関する記事です。
勉強会の名前を変えることで、より参加しやすいイメージを目指しています。
今後はAIに特化したイベントを開催し、その様子をレポートする予定です。
-
-
-
OpenAIによるWindsurf買収が中止になり、代わりにGoogleがWindsurfのCEOであるVarun Mohan氏らをGoogle DeepMindに迎え入れることになりました。
Mohan氏らはGoogle DeepMindでagentic codingに注力し、Geminiに携わる予定です。
GoogleはWindsurfの技術に対する非独占的ライセンスを取得しますが、Windsurfの支配権や出資は行いません。
-
-
-
ETH ZurichがオープンソースLLM構築のための国際サミットを開催しました。
EPFL、ETH Zurichなどの研究者が共同で開発した、完全にオープンなLLMのリリースを予定しています。
このモデルは透明性、多言語性能、幅広いアクセス可能性に焦点を当てています。
-
-
-
C++とのシームレスな相互運用を目指す新しい言語jankについての記事です。
jankはClojureをベースにしており、C++のライブラリやコードを直接利用できます。
この記事では、jankの最新の進捗状況と、C++との連携に関する具体的な例を紹介しています。
-
-
-
JPEGファイルを偽造する方法についての記事です。
構造化された部分と圧縮データの場所を示すタグを含むJPEGファイルのテンプレートを使用します。
ランダムなデータで「圧縮」領域を埋めることで、JPEGのように見えるものを作成します。
-
-
-
インドの航空事故調査局によるエア・インディア171便の墜落事故に関する予備報告書が発表されました。
報告書によると、離陸直後に燃料制御スイッチが「run」から「cutoff」に切り替えられたとのことです。
これにより両エンジンが推力を失い、パイロットの行動に注目が集まっています。
-
-
-
M4 Pro Mac miniのストレージを自分でアップグレードする方法を紹介しています。
ExpandMacMiniのDIYキットを使用することで、Apple純正よりも安価にストレージを拡張できます。
DFU restoreが必要ですが、手順は比較的簡単です。
-
-
-
Better Software Conference (BSC) 2025に関する情報です。
物理的な参加は招待制ですが、講演はライブストリームと録画で無料公開されます。
スウェーデンの魅力的な小都市で開催予定です。
-
-
-
Andrew Ng氏によるAIに関するYouTube動画です。
AI技術を活用してより迅速に開発を行う方法について解説されています。
YouTubeの利用規約やプライバシーポリシーにも言及があります。
-
-
-
この記事は、Macintoshの初期開発に貢献したBill Atkinson氏の知られざる側面を紹介しています。
彼は晩年、幻覚剤5-MeO-DMTを投与するためのLightWandというベイプペンの技術を開発していました。
彼のオープンソースなアプローチは、サイケデリック探求の民主化に貢献したと述べられています。
-
-
-
Pythonで辞書のアンパッキングを可能にするライブラリの紹介です。
`dict-unpacking-at-home`を使うと、辞書の値を直接変数に展開できます。
ただし、これはジョークパッケージであり、実用は推奨されていません。
-
-
-
Monorailは、CSSキーフレームアニメーションをインタラクティブなグラフに変換します。
GitHubリポジトリで詳細な使用方法を確認できます。
アニメーションの再生速度をインタラクティブに調整できます。
-
-
-
この記事は、Appleがデジタル市場法(DMA)にどのように対応しているかについて議論しています。
AppleはDMAの解釈に強く反発し、法を遵守するために必要な複雑なエンジニアリングは不可能だと主張しています。
この記事は、Appleが規制を回避し、自社の利益を優先する姿勢を批判的に分析しています。
-
-
-
OpenPipeのブログ記事です。
エージェントのための強化学習(RL)について解説しています。
より賢いエージェント開発に役立つ情報を提供します。
-
-
-
この記事はMacBookのサーマルペーストの交換について解説しています。
CPU温度が下がり、ファンの回転数も低下し静音化に繋がりました。
しかし、分解時にケーブルを破損するリスクがあり、注意が必要です。
-
-
-
バングラデシュでターメリックに鉛が混入している事例が発覚しました。
ニューヨークの刑事とカリフォルニアの学生が協力し、原因を究明しました。
鉛中毒は子供たちの健康に深刻な影響を与えるため、対策が急務です。
-
-
-
デジタルフィルタの概要を紹介するWebコンテンツです。
音声処理への応用を念頭に解説されています。
スタンフォード大学のCCRMAで公開されています。
-
-
-
McDonald'sの求人チャットボット「McHire」に脆弱性が発見されました。
6400万人以上の求職者のチャットが、脆弱な認証情報により漏洩した可能性があります。
IDOR脆弱性により、個人データやチャット履歴にアクセス可能でした。
-
-
-
ペンシルベニア州下院は、不正なサブスクリプションサービスを取り締まる法案を可決しました。
これは、消費者がオプトアウトしない限り自動的にサービスに登録される「ネガティブオプション」契約を取り締まるものです。
オンラインで契約したサブスクリプションは、オンラインでキャンセルできるようにする必要があります。
-
-
-
ヨーロッパで初めて、太陽光発電が最大の電力源となりました。
EUの電力の22%を供給し、記録を更新しました。
少なくとも13カ国で太陽光発電量が月間最高を記録しました。
-
-
-
Pangolinは、セキュアな分散ネットワーク上のプライベートリソースを公開するための、自己ホスト型のトンネル型リバースプロキシサーバーです。
IDとアクセス制御を備え、ポートを開放せずにリモートサービスへのアクセスを容易にします。
WireGuardトンネルによるリバースプロキシ、集中認証システム、シンプルなダッシュボードUIなどが特徴です。
-
-
-
128KBという厳しい制約の中でWebサイトを構築した経験について語っています。
Webフォントの代わりにシステムフォントを使用したり、フレームワークを使わずに独自の軽量ライブラリを開発したりするなどの工夫が紹介されています。
SVGの最適化やHTMLのミニファイ化など、徹底的に軽量化を追求した結果、低スペックな環境でも快適に動作するWebサイトを実現できたそうです。
-
-
-
著者はソーシャルメディア疲れを経験し、利用をやめる決意をしました。
本の宣伝のためにSNSを利用しましたが、期待した効果は得られませんでした。
今後はブログとニュースレターを通じて、より質の高いコミュニケーションを目指しています。
-
-
-
本記事は、LLM推論を本番環境で展開、拡張、運用するための実践的なガイドです。
コアコンセプトやパフォーマンス指標から、最適化技術、運用ベストプラクティスまで網羅しています。
LLM推論をより速く、安く、信頼性高くすることを目指すエンジニア向けです。
-
-
-
この記事では、数の数え方である長短の位取り記数法について解説されています。
幼少期に学んだ長位取りは、百万の累乗に基づいたもので非常に直感的でした。
しかし、現代のテクノロジーの世界では、短位取りが主流であり、その違いを理解する必要があります。
-
-
-
この記事は、日本のオーバーツーリズムが小規模ビジネスに与える影響について論じています。
観光客の増加は、地域住民との交流を阻害し、コミュニティを破壊する可能性があると指摘しています。
解決策として、観光客の分散や、地域への経済的貢献を促す政策を提案しています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より