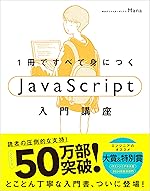-
-
この記事では、ローカルLLMの進化と活用方法を紹介しています。
GoogleのGemma 3n E4Bなどの比較的小さなモデルでも実用的な性能が出てきています。
ネット接続なしで利用できる点や料金がかからない点がメリットです。
-
-
-
この記事は、個人開発におけるドキュメントの重要性を解説しています。
Claude Codeを活用した開発効率向上のために、24種類ものドキュメントを事前に準備した事例を紹介しています。
技術設計、デザインシステム、ライブラリ対策など、具体的なドキュメント構成とその役割を詳細に解説しています。
-
-
-
開発未経験の筆者がDifyハッカソンで3位入賞した体験を記録しています。
CursorとAIを活用し、課題の深掘りや時間管理、Difyの操作方法などを学びました。
非エンジニアでもAIを信頼し、段階的な開発で成果を出せることを示唆しています。
-
-
-
AIが書いた怪談小説が面白いという記事です。
グーグルのGemini 2.5 Proを使って作成されたショートショートは完成度が高く、普通に読めます。
AIによる小説執筆がどこまで進んだかを紹介しています。
-
-
-
本番環境での問題解決にオブザーバビリティを活用する方法を紹介しています。
開発者やマネージャーがデータに基づいてシステムを理解し、改善に役立てる視点を解説。
具体的な可視化グラフの例や、導入ガイドへのリンクも提供しています。
-
-
-
情報システム部に対する意見への反論がまとめられています。
システム側の人間こそビジネスを理解し、要求定義や要件定義をすべきという主張です。
現場の機微や業務フローは情シス担当者にしか分からないと述べています。
-
-
-
中国各地で3Dプリンターを使った製品を大量生産する3Dファームが増加しています。
しかし、その増加によりバブル崩壊の危機も囁かれています。
安価な3Dプリンターと材料の普及が背景にありますが、量産には本来不向きなはずです。
-
-
-
ObsidianをLLM時代のナレッジベースとして活用する方法を紹介しています。
クリッピングからMarkdownへの変換、CLI連携の実践について解説されています。
Gemini CLIとPlaywright MCPツールを連携させ、WebページをMarkdown形式で完璧に取得する方法が示されています。
-
-
-
この記事はLLM推論に関する技術的なメモです。
BentoMLによるLLM Inference Handbookを参考に、LLM推論の技術をまとめています。
トークン化、推論の2フェーズ、API型とセルフホスト型、GPUメモリ計算、量子化、推論フレームワーク、推論メトリクスなどについて解説します。
-
-
-
この記事は、Amazon DynamoDBにおけるシングルテーブル設計とマルチテーブル設計について解説しています。
シングルテーブル設計がアプリケーションに役立つ場合や、複数のテーブルを使用した方が良い例を紹介しています。
DynamoDBのデータモデリング原則を理解し、最適なテーブル設計を選択するためのガイドを提供します。
-
-
-
AtCoder World Tour Finals 2025 HeuristicエキシビションでのAIと人間の対決を、運営側の視点からまとめた記事です。
OpenAIのエージェントは2位相当と優秀で、人間の良いアイデアを基に最適化すると更に良い結果が得られることが示されました。
しかし、時間をかけた人間はまだAIに勝て、問題設定によってAIの優位性が変わる可能性も指摘されています。
-
-
-
エンジニアがビジネス界隈に進出する際は、世の中の普通の人々と深く関わることが重要である。
社内ではロジックだけでなく、相手のロジックを理解する必要がある。
エンジニアが非エンジニアと関わる場を積極的に設けるべきである。
-
-
-
18年間不妊治療がうまくいかなかった夫婦がAIの力で妊娠しました。
AIが夫の無精子症から正常な精子を検出し、体外受精を成功させました。
新しいアプローチであるSTAR法は、不妊治療に新たな選択肢をもたらす可能性があります。
-
-
-
Obsidian 初学者勉強会に参加し、登壇した際の記録です。
自身の発表内容や他の参加者の発表内容についてまとめられています。
Obsidianの様々な活用方法を知ることができる記事です。
-
-
-
技術評論社から出版されたWeb API開発の実践ガイドです。
Software Designの特集記事をまとめたもので、Web API開発の知識が凝縮されています。
OpenAPI、gRPC、GraphQLなど、様々なWeb API技術を網羅的に解説しています。
-
-
-
この記事では、OpenAIの音声認識モデル「Whisper」を使って、音声をリアルタイムで文字起こしする機能を紹介しています。
イベントでの学びを深めるため、YouTubeや現地の音声を文字起こしし、Gemini CLIで要約する手法を解説しています。
仮想オーディオデバイスBlackHoleの導入方法や、実際のイベントでの使用感、課題点も共有しています。
-
-
-
この記事では、AGI(汎用人工知能)の実現に必要な能力について解説しています。
知能を「初めて遭遇する問題や新しい状況に対応する能力」と定義し、流動的知能の重要性を強調しています。
既存のAIベンチマークの限界を指摘し、新しいベンチマーク「ARC-AGI」シリーズを紹介しています。
-
-
-
この記事では、ChatGPTのDeep Researchの弱点を補完するScholar GPTを紹介しています。
Scholar GPTは最新の研究論文を素早く見つけ、要約・分析できます。
研究文書の読み込みやリンクの解析も得意で、効率的な学習をサポートします。
-
-
-
この記事では、AIエージェントを活用してSRE(サイト信頼性エンジニアリング)の業務を自動化する試みを紹介しています。
Azure SRE Agentを使用し、障害検知から復旧までの時間と労力を削減できることをハンズオン形式で解説しています。
将来的には、より多くの業務がAIエージェントに代替され、人間がより創造的な仕事に集中できる未来を期待しています。
-
-
-
GitHubはGoogleアカウントでのサインアップ、ログインを可能にしました。
GoogleアカウントをGitHubアカウントにリンクできます。
Visual Studio CodeユーザーはGitHub Copilotを試すのが簡単になります。
-
-
-
AWSはCloudWatch MCPサーバーとApplication Signals MCPサーバーという2つの新しいModel Context Protocol (MCP)サーバーの提供を開始することを発表しました。
これらのサーバーにより、AIエージェントは包括的なオブザーバビリティ機能を活用して、トラブルシューティングとモニタリングを自動化できます。
MCPサーバーを使用すると、AWS環境全体のメトリクス、アラーム、ログ、トレース、サービスヘルスデータを分析し、問題を迅速に特定できます。
-
-
-
AWS CLIを使用して、全てのリージョンでSSMドキュメントのパブリック共有をブロックする設定に変更する方法が紹介されています。
Security Hub CSPMにパブリック共有ブロック設定の確認コンソールが追加された背景も解説されています。
特定のリージョンのみ設定を変更する例も記載されており、実用的な内容となっています。
-
-
-
Terraform AWS Providerのallowed_account_idsに関する記事です。
この機能を使うことで、意図しないAWSアカウントへのリソース作成を防ぐことができます。
オペレーションミスを削減するための具体的な方法が解説されています。
-
-
-
Windows PowerToysのプレビューハンドラのバグが修正された。
このバグは、PowerToysをユーザーごとにインストールした場合に発生していた。
テキストファイルのプレビューがエラーになる問題が解決されている。
-
-
-
AI怪談を生成するためのプロンプトが紹介されています。
テーマはAIにより誘発される感情の探求で、現実と連続した恐怖や奇妙さを追求します。
幽霊や海外を舞台にすることは避け、日常に侵食するAIの恐怖を描くことが推奨されています。
-
-
-
本記事は、ObsidianとClaudeを活用したCode情報管理術を紹介しています。
ツールの連携方法や具体的な管理方法について解説。
効率的な情報管理を目指す方におすすめです。
-
-
-
Intelが最速Linux「Clear Linux」の即時終了を発表しました。
10年間、性能追求してきたプロジェクトですが、コスト削減のため幕を下ろします。
セキュリティパッチやアップデートは停止され、他のディストリビューションへの移行が推奨されています。
-
-
-
AWSの新しい無料プランが2025年7月に更新され、最大6ヶ月間、最大200ドルのAWSクレジットが利用可能になりました。
コンソールからチュートリアルを実施することで、100ドル分の追加クレジットを獲得できます。
セキュリティ対策を施した上で、AWSを試したい方にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
-
-
-
UI Toolkit を使って VR 空間で入力可能な World Space な UI を実現するための手順が解説されています。
Unity 6.2で、UI Toolkitを使用して、3D環境でのWorld Space に UIを設置できるようになりました。
VR環境でのUI Toolkit管理やWorld Space UI入力設定についても説明されています。
-
-
-
AIが生成した文章がつまらない原因として、トーンの一貫性のなさを指摘しています。
解決策として、バリデーションツールによるフィードバックループを提案しています。
AIが草稿を書き、ツールでチェックし、修正するサイクルを回すことで文章の質を高めることを目指しています。
-
-
-
SwiftUIでメニューバー常駐アプリの作成を試した記事です。
簡単なサンプルと右クリックでのContextMenu表示も実装しています。
MenuBarExtraAccessというパッケージを利用しています。
-
-
-
Ubuntuにインストールした際の環境構築に関する記事です。
ターミナルの設定、tilix、fish、starshipなどのカスタマイズについて解説されています。
Vimの設定については現在更新中のようです。
-
-
-
この記事は、TypeScriptの判別可能ユニオンを活用した状態管理について解説しています。
複雑なデータ構造の型安全な管理や、修正漏れの防止に役立つことが述べられています。
Zodライブラリとの組み合わせによるAPIレスポンスの検証についても紹介されています。
-
-
-
Microsoft Learn Docs の MCP Server で GitHub Copilot が Azure に詳しくなります。
Microsoft Learn のドキュメント検索と GitHub Copilot の Agent Mode を組み合わせて効率的に情報収集できます。
Azure MCP Server と組み合わせることで、Azure のベストプラクティスに沿った開発も可能です。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より