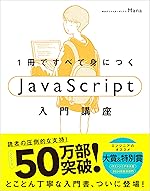-
-
この記事では、ClaudeとDraw.ioを活用し、業務フロー図の作成を効率化するプロンプトを紹介しています。
ワークフロー分析アシスタントとワークフロー図作成プロンプトを使用し、質問リスト化とAIへの丸投げでヒアリング漏れを防ぎます。
設計原則をプロンプトに埋め込むことで、レイアウトベースの作成を自動化し、若手でも高品質なフロー図を作成可能です。
-
-
-
OpenAIがオープンソースのAIモデル「gpt-oss」を発表しました。
大規模モデル「gpt-oss-120b」と中規模モデル「gpt-oss-20b」の2種類が公開されています。
推論機能に特化しており、高性能ながらも使いやすいモデルとのことです。
-
-
-
この記事では、改善要望における「Why」の重要性を解説しています。
「Why」を明確にすることで、最適な解決策を見つけ、開発スピードを上げることが可能です。
また、チーム全体の共通認識が生まれ、将来の拡張も容易になります。
-
-
-
TSMCの2nmプロセス技術情報が漏洩した疑いがあり、東京エレクトロンも捜査対象となっています。
台湾当局は国家安全法を視野に捜査を進めており、技術覇権を巡る競争の激しさを物語っています。
漏洩した技術は国家の経済安全保障を揺るがしかねない「国家核心重要技術」と見なされています。
-
-
-
Passkey認証におけるアカウント乗っ取り脆弱性(CVE-2025-26788)について、Non Discoverable Credentialフローとの混在に起因する問題を解説しています。
StrongKey FIDO Serverの脆弱性を例に、実装ミスがPasskey認証のセキュリティを損なう可能性を示唆しています。
攻撃者が用意した認証器で生成されたアサーションを利用し、被害者のアカウントを乗っ取る手口をソースコードレベルで解説し、対策を提示します。
-
-
-
このスライドは、Claude Code (aider/codex-cli など) をもっと活用しようという提案です。
Gitの有用性、特にディレクトリ構造を時間軸で行き来できる点が強調されています。
基礎を学ぶ機会がないという意見に惑わされず、LLMを活用してバッドノウハウを回避し、より良い時代を生きるべきだと述べています。
-
-
-
Anthropic社がClaude Opus 4.1をリリースしました。
agenticタスク、実際のコーディング、推論が向上しています。
API、Amazon Bedrock、Google CloudのVertex AIで利用可能です。
-
-
-
この記事では、Slack上で動くAI bot「resident-ai」を紹介しています。
チャンネルのCanvasを最大限に活用し、AIが情報を理解して対話を進めます。
異なるチャンネル毎に固有の個性を持ったAI botが実現されています。
-
-
-
Windows 11 Homeのセットアップ時にMicrosoftアカウントが必須だが、回避策を紹介します。
コマンドプロンプトから特定のコマンドを入力することで、ローカルアカウントを作成できます。
すでにMicrosoftアカウントでセットアップ済みの場合は、設定からローカルアカウントに切り替え可能です。
-
-
-
2700万パラメータの超小型AI「HRM」が登場しました。
このモデルは、複雑な推論タスクで大規模言語モデルを凌駕します。
人間の脳の階層的処理を模倣した構造が特徴です。
-
-
-
キリンが経営会議にAI役員を導入し、過去の議事録を学習させて議論に参加させる試み。
AIは複数の人格を持ち、経営層に多様な視点を提供するとのこと。
会議の効率化と意思決定の質向上を目指す取り組みとして、ネットでも話題になっている。
-
-
-
この記事は、AIによる開発の前提知識としてLLMのプロンプトエンジニアリングについて解説しています。
LLMの特性を理解することで、AIコーディングなどがより効果的になることを説明しています。
プロンプトの構造や組み立て方、LLMの特性など、開発に役立つ情報がまとめられています。
-
-
-
国産の電子回路・プリント基板設計アプリ「Quadcept」の最新版v11.0.0がリリースされました。
約6年ぶりのメジャーアップデートで、環境設定周りのリニューアルや図面比較機能の改善などが施されています。
無償版の「Quadcept Community」も提供されており、気軽に試すことができます。
-
-
-
無料3DCG統合環境「Blender 4.5」の使い勝手が大幅に向上したという記事です。
カーブオブジェクトのアクティブスプラインパネルがサイドバーに移動し、操作性が向上しています。
ヘアーカーブとグリースペンシルオブジェクトでもトランスフォームパネルが改善されました。
-
-
-
デジタル庁がiPhoneのマイナンバーカード確認機能を提供開始しました。
事業者は専用アプリで利用客のiPhoneをかざすだけで本人確認が可能です。
物理カード不要で、よりスムーズな本人確認が期待されます。
-
-
-
GIGAZINEの記事で、AIが就職面接を行う企業が増えていることが紹介されています。
求職者の中には、AI面接に拒否感を抱き、そのような企業を避ける傾向も出てきているようです。
企業側は効率化のためにAIを導入していますが、応募者とのミスマッチも生じている可能性があります。
-
-
-
この記事では、AIを活用した開発手法「バイブコーディング」の問題点を指摘しています。
バイブコーディングは手軽だが、技術的負債を増やす可能性があると警告しています。
AIを使いこなすには、人間が主体的に考え、学ぶ必要があると結論付けています。
-
-
-
この記事では、Claude Codeのレート制限を最大限に活用する方法を紹介します。
朝にClaudeに挨拶することで、業務時間内にClaude Codeを1.5倍活用できます。
週次レート制限導入により、ヘビーユーザーは影響を受ける可能性がある点に注意が必要です。
-
-
-
この記事では、企業におけるITツールの乱立、いわゆる“シャドーIT”問題に対するガートナーの解決策を紹介しています。
ガートナーは、デジタル・ワークプレイスを3つの層に分類し、管理することで、この問題を解決できると提唱しています。
特に、活動特化ツールの管理が重要であり、IT部門とユーザー部門の分業モデルがカギとなると解説しています。
-
-
-
LibreOffice WriterにMarkdownの読み取り機能を追加するパッチが提供されるようです。
Markdownは軽量マークアップ言語で、AIが出力するスタイルテキストの書式として目にすることも多いです。
来年のLibreOffice 26.2には間に合うかもしれないので期待したいです。
-
-
-
この記事では、MCP(Model Context Protocol)におけるエンタープライズ向け認可に関する最新の議論を紹介しています。
特に、Oktaからの提案であるSEP-646を中心に、IdP(Identity Provider)を活用した認可の集中管理の可能性について解説しています。
エンタープライズ環境でのMCP利用におけるセキュリティと管理の課題を解決するための重要な提案です。
-
-
-
MicrosoftがAIに代替される可能性のある職業と、比較的安全な職業を発表しました。
20万件を超えるAI利用データを分析し、AI適用性スコアに基づいてランキング化しています。
AIが得意とする知識労働と、身体性や暗黙知を必要とする労働の差が明確になっています。
-
-
-
マルウェアURLの安全な共有方法の標準化提案について解説されています。
URLを難読化して共有する際の共通ルールをRFCとして定めることで、誤クリックを防ぎます。
脅威インテリジェンスの共有と自動処理の促進に貢献することが期待されています。
-
-
-
OpenAIが公開したオープンソースモデル、gpt-ossシリーズの紹介です。
強力な推論、エージェントタスク、多様な開発者向けユースケース向けに設計されています。
Transformers, vLLM, PyTorch, Ollamaなど様々な環境での利用方法が解説されています。
-
-
-
OpenAIが開発した推論、エージェントタスク、開発者向けに設計されたオープンモデルシリーズであるgpt-ossの紹介です。
Apache 2.0ライセンスで、カスタマイズや商用利用が可能です。
推論の調整、CoTへのアクセス、ファインチューニング、エージェント機能、MXFP4量子化などの特徴があります。
-
-
-
AlibabaのAI開発チームQwenが画像生成AI「Qwen-Image」を発表しました。
Qwen-Imageはテキストの正確な描画に優れており、複数行の中国語や英語との同時描画が可能です。
画像生成や編集性能も高く、既存のモデルを超えるスコアを記録しています。
-
-
-
この記事は、エンジニアがマネジメントに移行する際の戸惑いと、それを克服するための書籍を紹介しています。
READYFOR株式会社のVPoE・EMである熊谷遼平さんが、マネージャーとしての意思決定や評価、市場価値への不安と向き合う上で助けになった10冊を厳選。
マネジメントの本質を捉え、組織全体で不確実性を受け入れ、本質的な課題を見極める思考の重要性を説いています。
-
-
-
IT系上場企業の平均年収を業種別にまとめた2025年版の記事です。
パッケージソフトウェア系、SIer、クラウド/通信キャリア系の企業が紹介されています。
各社の従業員数、平均年齢、平均勤続年数、平均年収が一覧で確認できます。
-
-
-
三井住友FGが中島達社長の発言を学習させた生成AI「AI―CEO」を7月から本格導入しました。
傘下の三井住友銀行の国内行員約3万人を対象に、業務上の相談などで気軽に活用してもらい、AIの全社的な浸透を図ります。
経営者目線での回答や企画のブラッシュアップ、音声アバターの活用も予定されています。
-
-
-
この記事では、AWSが開発したAIエージェントと連携したVSCodeベースのIDEであるKiroと、その特徴であるSpec駆動開発について解説します。
Spec駆動開発とは、要件定義・設計・タスク分割のドキュメントをAIが生成し、それに基づいてコーディングを行う手法です。
Kiroの登場によりAIコーディング界でSpec駆動開発が主流になる可能性や、Claude Codeなど他のツールへの影響についても考察しています。
-
-
-
Tailwind CSSで未定義のクラスを指定した際にエラーを出す方法を紹介しています。
eslint-plugin-better-tailwindcssを使用し、設定を調整することで対応できないケースにも対応しています。
カスタムルールを作成し、特定の変数名でのクラス指定を禁止する方法も解説しています。
-
-
-
この記事では、LLM(大規模言語モデル)の技術的な基盤と革新性について考察します。
LLMの登場により何ができるようになったのか、何が本質的に難しいのかを技術的観点から解説します。
プロダクト価値を発揮するための生成AI活用法について述べています。
-
-
-
ISTQB Testing with Generative AI 試験に合格した体験について書かれています。
生成AIをテストに活用するための知識や学習方法、試験の感想がまとめられています。
経験に基づいた知識に名前をつけることで体系化し、業務活用の方向性を確認できたと述べています。
-
-
-
AIで手相を読み解くWebアプリ「Palma」が個人開発されました。
スマホで手のひらを撮影するだけで、AIが手相鑑定をしてくれます。
古代の手相術と最新AI技術を組み合わせた自己分析ツールです。
-
-
-
この記事では、Vimで端末エミュレータのコピー機能を使う方法を紹介しています。
Vimの進化により、以前は複雑だった処理が簡潔に実装できるようになりました。
特に、getregion()やbase64_encode()といった新しい関数が便利です。
-
-
-
この記事では、LLMのコンテキスト制約がAIの性能低下の原因であることを解説しています。
Serena MCPというツールが、LLMのコード理解を向上させる仕組みを紹介しています。
Serena MCPは、コードの構造を理解し、ローカルで動作するためセキュリティも確保されます。
-
-
-
Figma Makeを使い、高齢者向けSNSアプリのUIを生成する実験を紹介しています。
AIに様々なプロンプトを与え、生成されるUIの変化を検証しています。
参考画像の利用やUIガイドラインの設定など、AIの活用方法を考察しています。
-
-
-
Google DeepMindが新しいワールドモデル「Genie 3」を発表しました。
このモデルは、多様なインタラクションを学習し、新たな可能性を開拓します。
ゲームやインタラクティブ環境における応用が期待されています。
-
-
-
base64エンコードされたJSON、証明書、秘密鍵を見つける方法について解説されています。
特定の文字列パターン(`ey`や`LS`)を手がかりに、デコードせずに判別するテクニックを紹介。
これにより、暗号化されたファイルに含まれる情報を迅速に特定できます。
-
-
-
Ollama Turboは、データセンター級のハードウェアを使用してオープンモデルを実行する新しい方法です。
大規模なモデルを高速に実行でき、OllamaのApp、CLI、APIと連携します。
Turboモードでは、クエリは記録または保持されません。
-
-
-
uBlock Origin Liteは、iOS App Storeで提供されているコンテンツブロッカーです。
開発者は一切のデータを収集しないと明記しており、プライバシーを重視するユーザーに適しています。
広告やトラッカーをブロックし、快適なブラウジング体験を提供します。
-
-
-
Deflateの代わりにZstandardやLZ4の使用を検討するというGitHubのissueです。
PNGの圧縮に関する議論のようです。
より効率的な圧縮アルゴリズムの提案が含まれています。
-
-
-
この記事は、第二次世界大戦中に英国のチャーチル首相に贈られるはずだったカモノハシの「ウィンストン」の死因を調査したものです。
当初、ドイツの潜水艦による爆撃が原因とされていましたが、新たな調査で輸送中の高温が死因であった可能性が示唆されました。
また、その後のカモノハシ外交の試みとその失敗についても触れられています。
-
-
-
Geminiアプリで、イラスト付きのオリジナル絵本を作成できるようになりました。
テキストで物語のアイデアを伝えるだけで、Geminiがカスタムアートとオーディオ付きの10ページの絵本を生成します。
子供向けの教材や、思い出を物語に変えるなど、様々な用途で活用できます。
-
-
-
RubyのJSON gem APIの問題点について解説しています。
特に、セキュリティリスクのある`create_additions`オプションや、重複キーの扱いなど、改善すべきAPI設計について議論しています。
`JSON::Coder` APIの導入により、より安全で柔軟なJSON処理が可能になることを提案しています。
-
-
-
Anthropic社がClaude Opus 4.1を発表しました。
エージェントタスク、コーディング、推論が向上しています。
API、Amazon Bedrock、Google CloudのVertex AIで利用可能です。
-
-
-
この記事では、AIがエンジニアの生産性を10倍に向上させるという主張に対する懐疑的な見方を示しています。
AIコーディングツールの過大評価、企業におけるソフトウェア開発の現実、エンジニアの真の価値について考察しています。
AIの導入による過度な期待が、エンジニアの不安を煽り、短絡的な思考を助長する可能性を指摘しています。
-
-
-
このWebコンテンツは、オズワルド・デ・アンドラーデの「人食い宣言」について解説しています。
ブラジルがポルトガルに発見される前から幸福を発見していたという主張は重要です。
この宣言は、ブラジルを人種が重要でなくなる楽園として描いています。
-
-
-
ロスアラモス国立研究所による動的イメージング技術に関する記事です。
爆発現象を捉え、物質の特性や物理を解析し、兵器の性能を評価します。
pRad、DARHT、Scorpiusという主要施設が紹介されています。
-
-
-
HIV治療において、子供たちが鍵を握る可能性が指摘されています。
抗レトロウイルス薬を早期に投与された子供たちの一部は、ウイルスを抑制できるようです。
これは、HIV治療の新たな道を開くかもしれません。
-
-
-
C言語を学びながら、独自のLispプログラミング言語を構築する方法を解説しています。
1000行のコードで、プログラミング言語の仕組みを理解できます。
オンラインで無料で読めるだけでなく、印刷版や電子書籍版も購入可能です。
-
-
-
アメリカ政府がTSMCに対し、Intelへの49%出資を圧力をかけているという報道です。
これは、台湾への関税軽減の条件として提示されているとのことです。
Intelの経営状況を鑑み、アメリカ国内の半導体サプライチェーンを維持するための措置と見られています。
-
-
-
WindowsのAFD.sysドライバの内部構造を調査する連載記事の第1部です。
Winsockの代わりに、AFD.sysに直接I/Oリクエストを送信してTCPソケットを作成する方法を解説しています。
これにより、アンチチートやアンチマルウェアによるフックを回避し、Windowsのネットワーク処理の理解を深めることができます。
-
-
-
Whittleは、新しい単語ゲームです。
毎日更新される6つの単語パズルに挑戦できます。
シンプルなインターフェースで、気軽に楽しめます。
-
-
-
オープンソースは学習や可視性において良いことだと考えられています。
しかし、公開したことを後悔した経験はありますか?
保守の負担、不適切なユーザー、予想外の使用方法など、経験談を聞きたいです。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より