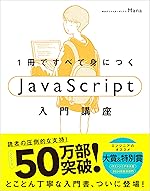-
-
Kindleの蔵書が増え、理想の本棚アプリが欲しくなった筆者が、バーチャル本棚アプリを開発した経緯を紹介しています。
Kindleの蔵書リストやハイライトのインポート、データのエクスポート、読書メモ、本棚のWeb公開など、自身が欲しい機能を盛り込んだアプリです。
GitHubでソースコードを公開し、誰でも自分の本棚を作れるようにしました。本を並び替えたり、コメントを追加したり、デジタルならではの自由な本棚作りを楽しめます。
-
-
-
OpenAIがLLMの「幻覚」に関する論文を公開しました。
LLMがもっともらしく聞こえる誤った情報を生成する理由を解明しようとしています。
評価方法の抜本的な見直しを提言し、不確実性を表明する能力を評価するよう促しています。
-
-
-
この記事では、生成AIをコーディング以外の分野で活用する方法について解説されています。
特に、不確実性の高い仕事や、人間が均質なアウトプットを出すのが難しい仕事でのAIの活用が推奨されています。
Logseqなどのツールを用いてInputを整備し、AIとの対話を通じて思考を深める方法が紹介されています。
-
-
-
AIエンジニアリングスキルを身につけるための学習過程をアウトプットした記事です。
Pythonでのプロジェクト管理にuvを使い、コード品質管理にRuffを使用します。
静的コード解析・型チェックをGit hooksに組み込む方法も紹介します。
-
-
-
この記事では、ローカルLLMを動かすためのアプリ「LM Studio」の使い方を解説します。
高性能な「Google Gemma 3n E4B」を例に、導入からチャット開始までの手順を紹介します。
ローカルLLMは自分のPC上で無料で使えるChatGPTのようなもので、個人情報も安心して処理できます。
-
-
-
GitHubのSpec Kitを使い仕様駆動開発を試した記事です。
AIと対話しながら仕様書を作成し、その仕様に基づいてコードを生成します。
仕様駆動開発は要件を明確にし、仕様書を信頼できる情報源として運用できます。
-
-
-
GitHubがリリースしたSpec Kitは、Spec駆動開発を支援するツールです。
他のコーディングエージェントにSDDを組み込むためのアドオンとして機能します。
この記事では、Spec Kitの導入から操作方法、そして実際の開発例までを解説します。
-
-
-
Vimの操作を効率化するためのテクニックと考え方をまとめた記事です。
ドットコマンド、オペレータとテキストオブジェクトの組み合わせ、ビジュアルモードなどを解説しています。
Vimの知識を深め、編集効率を向上させたい人におすすめです。
-
-
-
AIとの会話で一度失敗した場合、そのセッションを打ち切る方が良いという記事です。
AIは過去の文脈を引き継ぐため、失敗体験が後の会話に影響を与える可能性があります。
新たなセッションで、より良いAIとのコミュニケーションを目指しましょう。
-
-
-
国立環境研究所がAIでセミの鳴き声を種類特定する技術を開発しました。
5種類のセミの鳴き声をAIに学習させ、複数のセミが合唱する中でも聞き分けられます。
気候変動が生態系に与える影響を知る手がかりになると期待されています。
-
-
-
iPad mini 5を手書きデジタルノートとして使い始めた経緯と、E-InkタブレットBigme B7との比較が書かれています。
Bigme B7の使用感からiPad mini 5へ移行した理由や、iPad mini 5の機種選び、アクセサリー類についても触れています。
実際にiPad mini 5を使ってみた感想や、Goodnotesとの連携、ケースの使い勝手などがまとめられています。
-
-
-
元マッキンゼーのビジネスパーソンがAndroidに乗り換えた理由を紹介。
iPhoneの独占ビジネスに対し、Androidは競争原理で質が高いと述べています。
AIの恩恵や日本語入力の快適さなど、Androidの優位性を強調しています。
-
-
-
9月8日の未明から明け方にかけて「皆既月食」が日本各地で観測できます。
日本全国で見られるのは2022年の11月8日以来、3年ぶりとのことです。
ウェザーニュースのYouTubeチャンネルなどでライブ配信も行われます。
-
-
-
Go言語の解説本で、一段レベルアップしたいGo言語ユーザー向けです。
関数やパッケージの使い方、並行処理、テストなどの基本を解説します。
CLIアプリやWebアプリの開発、便利なパッケージも紹介しています。
-
-
-
npm Trusted Publishingが一般公開され、OIDCを使ってnpmトークンなしでCI/CDからパッケージを公開できます。
この記事では、npm Trusted Publishingの仕組み、設定方法、リリースフローを紹介します。
設定にはnpmjs.comでのTrusted Publisher設定と、CI/CDワークフローの設定が必要です。
-
-
-
エムスリーのUnit7チームが開発したAIレビュアー育成コマンドを紹介しています。
過去のレビュー内容をAIに学習させ、プロンプトを自動更新することでチームの文脈をAIに理解させます。
チーム固有の暗黙知や作法をAIが学習し、より最適化されたレビューが可能になることを目指しています。
-
-
-
GIGAZINEの記事で、50年以上前の卓球ゲーム「ポン」をクローン化。
ニューラルネットワークを使用しているとのことです。
AI技術の応用事例として興味深い内容です。
-
-
-
PostgreSQL拡張機能pg_duckdbのバージョン1.0がリリースされ、DuckDBのベクトル化された分析エンジンをPostgreSQL内で直接利用できるようになりました。
PostgreSQLが得意とするトランザクション処理を継続しながら、効率的なアドホッククエリを実行できます。
MotherDuckとの統合強化、より多くのデータ型のサポート、安定性の向上、並列テーブルスキャンを含むパフォーマンスの改善が図られています。
-
-
-
台湾メディアPCDIY!がWindows11 24H2環境でのSSD障害を再現したと報道しています。
原因はエンジニアリングサンプル版のファームウェアだったとのことです。
しかし、一般ユーザー環境での同様の報告もあり、謎は残ります。
-
-
-
ブラジルのアマゾン地域で乾季の雨量が減った原因の約75%は森林伐採によるものです。
世界的な気候変動よりも影響が大きいと評価されています。
COP30でも議論される予定で、森林伐採の影響の大きさと気候変動との関係性が重要視されています。
-
-
-
テスラの完全自動運転(FSD)は、他の自動車メーカーとは異なるアプローチを採用しています。
その違いは、LiDARなどの高精度センサーに頼らず、カメラとAIによる画像認識に依存している点です。
この方式はコストを抑えられる反面、悪天候や不測の事態への対応が難しく、安全性の面で課題が指摘されています。
-
-
-
組織変革における個人のあり方について考察されています。
変化の時に自分自身がどうありたいかを考える重要性が述べられています。
Speaker Deckのプレゼンテーション資料です。
-
-
-
この記事では、生成AI利用者が「AIメンタル不調」に陥る可能性について考察しています。
特に、AIが妄想の形成を助長する「人間とAIによる妄想の共同創造」に焦点を当てています。
OpenAIがAIの安全対策を強化する背景と、AIメンタル不調の定義について解説しています。
-
-
-
2025/09/06 フロントエンドカンファレンス北海道2025の登壇資料です。
HTMLの品質指標を作ることで、アクセシビリティ対応のための土台を作成しました。
クライテリアを作ることで、自分たちの立ち位置を理解し、改善の種が見つかりました。
-
-
-
EmbeddingGemmaはデバイス上のAI向けに設計されたオープンな埋め込みモデルです。
308Mのパラメータで高効率、オフライン動作、様々なツールとの連携が特徴です。
RAGパイプラインの品質向上に貢献し、多様なアプリケーションに対応可能です。
-
-
-
Cloudflare Agentsの基本的な使い方を紹介しています。
エージェントのセットアップから、実際の活用例までを解説。
Cloudflare Workersとの連携についても触れています。
-
-
-
LeetCodeを解きながら書き留めてきたJavaScript Tips集です。
チーム開発で可読性が重視される点も考慮されています。
様々なJavaScriptのテクニックが紹介されています。
-
-
-
フロントエンドカンファレンス北海道2025のオンライン参加レポートです。
イベントの様子や発表内容がまとめられています。
鮮度を重視した情報提供が特徴です。
-
-
-
Pico CSSは、HTMLタグを直接スタイルし、`.classes`の使用を最小限に抑えた軽量CSSフレームワークです。
依存関係やJavaScriptなしで動作し、HTMLマークアップだけでエレガントなスタイルを実現します。
レスポンシブ対応で、画面幅に応じてフォントサイズや間隔が自動的に調整され、ライト/ダークモードもサポートしています。
-
-
-
1991年のラジオ Shackの広告に掲載されていたものが、現在ではほとんどスマホでできるようになったという記事です。
当時3054.82ドル相当のものが、今ではスマホ一つで済むようになりました。
技術の進歩を実感できる内容となっています。
-
-
-
MacBookには、ディスプレイを開いた角度を検知するセンサーが含まれているようです。
公式に公開されているAPIではないようです。
ディスプレイを閉じた瞬間に木製のドアが閉じる音を出すことに成功しました。
-
-
-
この記事は、ChatGPTのGPT-5が検索において驚くほど優れている点を紹介しています。
著者はGPT-5を「リサーチゴブリン」と呼び、その能力を高く評価しています。
具体的な検索例を挙げながら、GPT-5の検索能力がいかに優れているかを解説しています。
-
-
-
ログから機密情報を排除する方法についての記事です。
セキュリティ対策として、単一の解決策ではなく多層防御の重要性を説いています。
データアーキテクチャ、データ変換、ドメインプリミティブなど、10個の具体的な対策を紹介しています。
-
-
-
GitHubリポジトリをPDFとして印刷できるWebサービスです。
お気に入りのリポジトリを美しい形式で印刷できます。
GitHubアカウントでサインインして利用できます。
-
-
-
1986年のソフトウェア工学に関する論文です。
ブルックスは1987年に発表した『人月の神話』の著者でもあります。
ソフトウェア開発において万能の解決策はないことを記した影響力のある論文です。
-
-
-
CSIROとSwinburneの研究者が火星の物質から金属を生成する方法を研究しています。
火星の居住地建設には大量の金属が必要ですが、地球からの輸送は困難です。
研究チームは、火星のレゴリス模擬物質を使用して鉄の生成に成功しました。
-
-
-
世界の海底ケーブルの分布図。
国や地域を選択すると、ケーブルの詳細が表示されます。
ケーブルの名前、運用状況、製造業者などの情報が確認できます。
-
-
-
モバイル向けに設計されたWebアプリです。
スマートフォンのカメラでQRコードをスキャンして利用できます。
デスクトップでも利用可能です。
-
-
-
SQLiteはTCLの拡張として生まれ、その設計はTCLに影響を受けています。
現在、SQLiteは内部でTCLを使用していませんが、開発プロセスはTCLに大きく依存しています。
SQLiteのソースコードの多くはTCLで書かれており、テスト、ドキュメント生成、開発に利用されています。
-
-
-
GPUはデータ処理を高速化しますが、データは単一GPUサーバーの容量を超えて増大しています。
NVIDIAとAMDは、データ移動を最適化する分散ランタイムの開発競争をしています。
Voltron DataのTheseusは、データ移動を重視した設計で、大規模なデータ分析とAIに最適です。
-
-
-
Flixというプログラミング言語を用いて、Algebraic Effectsを実際のソフトウェア開発にどのように活用できるかを紹介しています。
Algebraic Effectsを使用することで、コードのテスト容易性、コードの可視性、ユーザー定義の制御フロー抽象化が可能になります。
Flixは、関数型、論理、命令型プログラミングのパラダイムをサポートし、Algebraic Effectsを言語の基盤としています。
-
-
-
Prix Ars Electronica 2025の受賞作品を紹介しています。
Frode OldereidとThomas Kvamによるロボットインスタレーション「Requiem for an Exit」について解説されています。
技術、イデオロギー、集合的記憶の交差点を探求する作品です。
-
-
-
SQLiteのデータベースファイルフォーマットについて解説されています。
データベースファイルの構造、ヘッダー情報、B-treeページなど詳細な情報が記載されています。
ロールバックジャーナルやWrite-Ahead Log(WAL)についても触れられています。
-
-
-
サーバーレス環境での予想外の請求に関する事例集です。
WebflowやFirebase、Vercelなどでの高額請求の事例が紹介されています。
予期せぬ事態で多額の費用が発生するリスクについて知ることができます。
-
-
-
AI開発競争で、巨大IT企業がデータセンターを建設しています。
電力会社はデータセンター向けに電力供給で利益を上げようとしています。
一般消費者がデータセンター向けの電力コストを負担する仕組みを解説します。
-
-
-
猫に鈴をつける寓話は、猫の接近を警告するために猫の首に鈴を付けることを提案する物語です。
しかし、誰もその役割を担おうとしないという教訓を含んでいます。
この寓話は、実行可能性を考慮せずに理想的な結果だけを評価することの愚かさを教えています。
-
-
-
GarminがAppleに先駆け、衛星接続スマートウォッチを発表しました。
Fenix 8 Proは、衛星および携帯電話接続機能を備えた初のスマートウォッチです。
緊急時には、衛星または携帯電話接続を介してGarmin Responseセンターにメッセージを送信できます。
-
-
-
Microdotは、標準CPythonとMicroPythonをサポートする非常に小さなWebフレームワークです。
IoTデバイスから大規模なクラウドサーバーまで、幅広いシステムで使用できます。
Flaskに触発されており、Flask愛好家はMicrodotに多くの共通点を見出すでしょう。
-
-
-
亡き母の遺品を売る時の複雑な感情が綴られています。
銀食器や中国製の食器など、思い出の品々を手放す決意が語られます。
技術の進歩と社会の変化による価値観の変容も考察されています。
-
-
-
MVCのSmalltalk版とCocoa版の違いについて解説されています。
Smalltalk版MVCの構造と、モデル、ビュー、コントローラーの役割を説明しています。
モデルがUIに依存せず、再利用性を高める重要性について述べられています。
-
-
-
データ型とそれに対する操作の抽象化設計について解説されています。
既存のコードを変更せずに新しい型や操作を追加する問題「Expression Problem」に焦点を当てています。
オブジェクト指向と関数型プログラミングでの問題点と、Clojureでの解決策が示されています。
-
-
-
90年代半ば、佐々木美穂はゲーム会社アトラスに勤務していました。
彼女は女子高生に人気の可愛いステッカーに触発され、プリント倶楽部のアイデアを思いつきました。
そして、上司に提案したところ、それがきっかけでアトラスはアーケード市場に参入することになりました。
-
-
-
この記事では、Zigを使用してLinuxでのファイルIOパフォーマンスを最大化する方法を解説しています。
io_uringを用いた実装について、ベンチマーク結果をFioと比較しながら詳細に説明しています。
ポーリングIOや登録済みバッファの使用など、パフォーマンス向上のための重要な要素に焦点を当てています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より