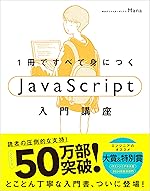-
-
AIをシステム開発に活用するためのノウハウがまとめられています。
AIエディタCursorを1年以上活用した事例を基に、現実的なシステム開発でのAI活用法を解説。
AIのための仕様書作成、モノレポ構成、テスト、静的型付け言語の採用など、具体的なコツを紹介しています。
-
-
-
ターミナルで使用できる便利ツールを、筆者の趣味で厳選して紹介しています。
`btop`, `ctop`, `oha`, `lazygit`, `yazi`など、日々の作業を効率化するツールが満載です。
記事の後半では、ターミナルを彩る`lolcat`や`cmatrix`といった面白コマンドも紹介しています。
-
-
-
米テスラ株が2カ月半で4割安と急落しています。
マスクCEOとトランプ大統領の関係が嫌われ、テスラ車の販売が急減していることが原因とみられています。
リベラル層に人気のテスラ車は、マスク氏のトランプ氏への接近でユーザーを困惑させています。
-
-
-
この記事では、X(旧Twitter)に頼らずにAI関連情報を効率的に収集できる代替ソースを紹介しています。
arXiv、Reddit、GitHub、ニュースサイト、技術ブログなど、様々な情報源を分類し、それぞれの特徴や活用法を解説しています。
最後に、これらの情報源を一元的にまとめて閲覧できるWebアプリ「nook」を紹介しています。
-
-
-
仮想通貨取引所Bybitがハッキングされ、2200億円相当のイーサリアムが盗難されるという事件が発生しました。
FBIは北朝鮮のハッカー集団の犯行と発表し、コールドウォレットが破られたことが衝撃を与えています。
盗まれた資金は前例のない速さで世界中に分散され、市場に不安が広がっています。
-
-
-
この記事では、生成AIに対する絵描きのnatsuki氏のスタンスと意見が述べられています。
一部の生成AIとその推進派を最低最悪だと感じている理由を、自身の研究経験を踏まえて解説しています。
倫理観の欠如、著作権侵害、悪用例など、生成AIの多くの問題点を指摘し、適切な規制の必要性を訴えています。
-
-
-
ローカルLLMを動かすためにVRAM40GBのPCを構築した記録。
RTX4070Ti SuperとRTX3090を組み合わせてVRAMを増強。
PCの選定からGPUの増設、電源の問題まで、構築の顛末を詳細に解説。
-
-
-
2025年3月1日、JAWS DAYS 2025で発表された資料です。
AIエージェント時代のエンジニアを目指す内容です。
Agentic WorkflowsからAmbient Agentsまで、基礎と実践を50分で学べます。
-
-
-
PHPにおけるテストに関する発表資料です。
テストの重要性や具体的なテスト手法について解説されています。
より良いテストコードを書くためのヒントが得られます。
-
-
-
Cursor Directoryは、様々なプログラミング環境のためのプロンプト集です。
TypeScriptやPython、Reactなど、多岐にわたる技術が網羅されています。
Web開発からゲーム開発、AI関連まで、幅広い分野のカテゴリーが見つかります。
-
-
-
フロントエンドにおける日時処理についてのプレゼンテーション資料です。
2025年版としてアップデートされています。
Speaker Deckで公開されています。
-
-
-
Web3のマルウェアの解析記事です。
ウォレット情報だけでなく、キーロガーやリモートデスクトップの奪取など、多岐にわたる攻撃が行われることが判明しました。
evalだけでなく、様々なコード実行手段があり、全開発者が警戒すべきと結論付けています。
-
-
-
Socketの仕組みについて解説されています。
domain, type, protocolなどの要素について説明しています。
ネットワークプログラミングの基礎を理解するのに役立ちます。
-
-
-
Go 1.24で導入されたGo製ツールの管理機能について、その概要と便利なポイントを紹介しています。
この機能を使うことで、Go製のツールのバージョン管理がより手軽になり、標準機能として提供されるため、サードパーティのツールを導入する必要がありません。
Go Modulesの機能の一部として提供されるため、既存の仕組みを流用でき、DependabotやRenovateによる自動更新も可能です。
-
-
-
この記事では、メモリの役割やデータの格納方法について解説されています。
スタックメモリとヒープメモリの違い、アドレスの概念、メモリレイアウトの構成要素を学ぶことができます。
アロケータの役割やメモリ管理の重要性についても触れられています。
-
-
-
この記事では、米政府のレガシーシステムであるCOBOLが抱える課題について解説しています。
社会保障制度を支えるCOBOLコードには、日付の標準化された方法がなく、1875年5月20日がプレースホルダーとして使用されることがあります。
記録の間違いは多いものの、不正受給は自動システムによってブロックされており、社会保障給付金を受け取っている吸血鬼は存在しないと結論付けています。
-
-
-
この記事では、説明が上手くなる「ファインマン・テクニック」を紹介しています。
ファインマン・テクニックは、学んだ内容を簡単な言葉で説明することで理解を深める学習法です。
プレゼンや会議での発表内容を「短く、わかりやすく、伝わるかたち」に変えるのに最適な方法です。
-
-
-
Deno、Pglite、Drizzle を使用して依存の少ないDBアプリを作成する方法を紹介しています。
PgliteはPostgresをwasmコンパイルしたもので、denoとの組み合わせで手軽にDBツールを構築できます。
この記事では、環境構築からマイグレーション、テストコードの作成までを解説しています。
-
-
-
コードレビューで避けるべき3つの行為を紹介しています。
ローカルでの動作確認をしない、安易な妥協をしない、代わりに実装しない、です。
これらを避けることで、効率的かつ効果的なレビューを目指します。
-
-
-
このプレゼンテーションは、サイト信頼性エンジニアリング(SRE)とAmazon Web Services(AWS)に関するものです。
SREの原則と、AWSの各種サービスを活用した実践方法について解説されています。
AWS環境におけるシステムの信頼性向上に役立つ情報が満載です。
-
-
-
CSSでインラインの条件分岐を可能にする`if()`関数についての記事です。
`if()`関数は、`supports()`、`media()`、`style()`、`else`の4つの条件を指定できます。
コンテナスタイルクエリと比較して、コードの記述量が少なく、フォールバック値が明確になる利点があります。
-
-
-
Datadog Continuous Profilerを活用し、Goのiterator導入でCPU時間を57%短縮しました。
メモリ確保量も99.4%削減という大幅な改善を達成しました。
性能改善と今後の安定した機能追加に繋がることが期待されます。
-
-
-
サンワサプライのプログラマブルキーボードは、3つのキーにショートカットや文字列を割り当てられます。
Excel作業などで繰り返し行う操作を効率化し、作業ストレスを軽減します。
キーの打鍵感やバックライトなど、使いやすさにもこだわったアイテムです。
-
-
-
コードレビューが苦手な人へ、丁寧なプルリクエストでチームの生産性向上を目指す方法を紹介。
コードレビューをつらく感じる原因を分析し、プルリクエスト作成者が意識すべきポイントを解説。
レビューの効率を高め、チーム全体の開発速度を上げるための具体的なアプローチを提案します。
-
-
-
アジャイル開発チームにおけるテスト戦略について解説されたプレゼンテーション資料です。
テスト戦略の重要性と、誰がその役割を担うべきかについて議論されています。
Speaker Deckで公開されており、スライド形式で情報がまとめられています。
-
-
-
PLAUD NotePinは、チャット式AIとの対話や検索で瞬時に必要な情報を提示します。
煩わしい情報管理から解放され、常に結果だけに集中できます。
AIを活用して効率的な情報管理を実現するツールです。
-
-
-
Sambaを用いてActive Directory互換環境を構築する方法を解説する記事です。
Samba ADのメリット・デメリット、構築手順、ドメイン参加について説明しています。
Windows ServerなしでAD環境を構築したい場合に役立つ情報が満載です。
-
-
-
国立国会図書館のPDF送信サービスを利用した体験談です。
PDFのダウンロードから料金支払いまでの一連の流れが記載されています。
著作権に関する補償金の問題点にも触れられています。
-
-
-
この記事では、創作活動を行う上での健康管理とドーパミンの維持について、筆者の経験をもとに解説されています。
身体の声に耳を傾け、痛みなどのアラートを無視しないこと、スケジュール管理や環境管理を徹底することの重要性が述べられています。
また、回復にお金をかけることの有効性や、カフェイン摂取の注意点など、具体的な対策も紹介されています。
-
-
-
ゲーム開発で活用できる線形代数の知識がつまった新刊書籍の紹介です。
株式会社セガ開発技術部課長である山中 勇毅氏が、従来の教科書にとらわれない形式で解説されています。
数学を活かす現場で役立つ内容です。
-
-
-
ピーター・ティールが創業したパランティアCEOの自社宣伝本に関する記事です。
テクノリバタリアンを理解するための本として紹介されています。
YAMDAS現更新履歴からの情報です。
-
-
-
この記事では、Firefox Syncサーバーをセルフホストする方法を紹介しています。
公式ドキュメントがわかりにくいものの、コミュニティの努力により実現可能です。
Dockerとデータベース管理に慣れていなくても、手順を追えば構築できます。
-
-
-
この海外記事では、住宅不足が現代社会の様々な問題の根源にあると主張しています。
住宅不足は、生産性の低下、イノベーションの阻害、不平等、地域格差、出生率の低下、肥満、気候変動など、多岐にわたる問題を引き起こすと述べています。
住宅供給を増やすことで、これらの問題の多くを解決し、人々の生活を大幅に改善できる可能性を示唆しています。
-
-
-
Claude CodeのソースコードをLLMで解析し、TypeScriptに変換する試みを紹介している海外記事。
難読化されたコードをLLMを使って可読性の高いコードに変換する手法を解説しています。
この技術を使うことで、既存のソフトウェアをリバースエンジニアリングできる可能性を示唆しています。
-
-
-
この海外記事では、AIを活用してソフトウェアを開発する新しいアプローチ「Vibe Coding」を紹介しています。
Vibe Codingは、プログラミングの知識がなくても、AIとの対話を通じて機能的なアプリやツールを構築できる手法です。
AIコーディングプラットフォームの選択、プロンプトの作成、反復的な改善を通じて、アイデアを具現化する方法を解説しています。
-
-
-
Maestroは、モバイルとWeb向けのシンプルで効果的なUIテストフレームワークで、AppiumやEspressoなどの先行技術から学んでいます。
UI要素の不安定さや遅延に対して耐性があり、テストの実行時に自動的に待機する機能を備えています。
YAMLファイルでテストを定義でき、シンプルなセットアップで高速な反復テストが可能です。
-
-
-
このブログ記事では、WASMとOpenGLを使って100万個の球体をレンダリングする実験について紹介されています。
WebGLへの移植の過程で遭遇した、テクスチャの歪みやVAOの再利用に関する問題とその解決策を解説しています。
OpenGLとWASMに関する学習リソースも紹介されています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より