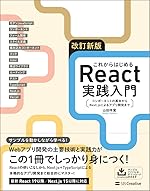-
-
TOEIC600点から875点へ、3ヶ月で270点アップしたAI活用勉強法を紹介。
仕事終わりに1日1時間、AIと映画・ドラマを活用して英語の瞬発力を鍛えます。
AI英単語アプリ開発やChatGPT英会話など、具体的な勉強法が満載です。
-
-
-
Gemini3以降に書かれた記事から、業務に役立つ生成AIの実践活用記事を紹介。
Gemini3のビジネスシーンへの影響や、NotebookLMの進化による業務利用の拡大について解説。
Nano Banana Proによる画像生成や、Gemを活用したマイアプリ作成、人事業務へのAI組み込み事例も紹介。
-
-
-
Excelの独特な仕様や操作性に対する不満が述べられています。
特に、他のツールとの連携の難しさや、直感的に理解しにくい部分が指摘されています。
Excelを使う上での苦労や、代替ツールへの期待が込められた記事です。
-
-
-
Claude Codeを中心としたAIコーディングの実践的な手法を紹介。
開発プロセスを効率化するための並列開発、プロンプト管理、レビューの自動化などの工夫を解説。
特に、git worktree、Markdown、subagent、Claude Skillsなどのツールを活用した具体的な運用方法が解説。
-
-
-
AIがコードを書く時代における要件定義の重要性を解説しています。
「何を作るべきか」を選ぶことの価値を強調しています。
IPAのガイドを参照しつつ、AI時代における要件定義の本質を考察しています。
-
-
-
AIコードエディタを手掛けるCursorのCEOが、AIへの過度な依存に警鐘を鳴らしました。
AIに全てを任せてコードの中身を確認しない開発手法は、不安定な基盤を積み重ねると指摘しています。
AI支援コーディングには段階があり、高度な開発ではリスクが高いと述べています。
-
-
-
OAuthとOIDCの違いについて解説されています。
OAuthは認可、OIDCはIdPが認証したユーザー情報をやり取りするための仕様と説明しています。
より理解を深めるために必要な前提知識についても触れられています。
-
-
-
2025年に読んでよかった本を紹介します。
AI時代だからこそ基礎的な知識を体系的に学ぶことの重要性を説いています。
投資、セキュリティ、思考法、組織論、小説など幅広いジャンルの書籍が紹介されています。
-
-
-
AI駆動開発を全社に浸透させ、組織の力に変えるための具体的な指針を解説。
クラスメソッドでの実践も踏まえ、トップダウンとボトムアップの連携や、実践の重要性を説明。
AIアシストからAIネイティブな開発への移行、外部連携の重要性についても解説。
-
-
-
Rustで簡易なグリーンスレッドスケジューラーを作成する過程を紹介しています。
高級言語Rustからアセンブリまで幅広く触れ,低レイヤー操作を学習できます。
システムコールやメモリ管理など,周辺知識も習得できるためシステムプログラミングの入門に最適です。
-
-
-
Active Directory環境を縮小し、Entra IDへの移行について解説されています。
Entra IDに移行することで、多要素認証やJust-In-Timeの特権アクセスなどが利用可能になります。
AD縮退の5つのフェーズに分け、クラウド接続から100%クラウドへの移行ステップを紹介しています。
-
-
-
AIが書いた文章か人間が書いた文章かという議論に対する意見。
AIによって生成されたコンテンツの価値を問う。
感情的な反応よりも内容そのものを重視すべきという主張。
-
-
-
社内ドキュメントの視認性の低下とキーワード検索の課題を解決するGoogleのNotebookLMの活用事例を紹介。
NotebookLMを情報の統合と対話型の検索エンジンとして利用し、資料を一本化する方法を解説。
検索体験向上とメンテナンスコスト削減というメリットが期待できます。
-
-
-
mrubyはRuby言語の軽量実装です。
アプリケーションにmrubyをリンクして埋め込むことができます。
mrubyはMITライセンスでリリースされています。
-
-
-
エンジニアのGitHub Access Token漏洩が根本原因となったAPI改ざん事件について解説。
攻撃の流れを図解し、多層防御による具体的な対策を予防、被害軽減、検知・対応の各層で紹介。
CI/CDのセキュリティ強化、OIDC連携、実践的な情報が満載。
-
-
-
AI導入における「ドアマンの誤謬」について解説されています。
AIが本質を理解せず、表面的なパターン認識で誤った判断を下す問題を指摘しています。
AI導入の際には、その限界を理解し、適切な設計と運用が重要であると述べています。
-
-
-
筆者が30年分のメールを整理したところ、75万通ものメールが蓄積されていました。
ローカルAIで処理するには絶望的な量であり、クラウドの利用が現実的のようです。
個人のPCはAIの推論に使い、学習はクラウドで行うという使い分けが重要になると筆者は考えています。
-
-
-
個人開発者によるMMORPG『Dreadmyst』が注目を集めています。
ゲームエンジンからシステムまで全て自作されており、コードは8万行に及ぶとのことです。
2026年1月9日にSteamで基本プレイ無料でリリース予定です。
-
-
-
テキストレンダリングがいかに難しいかを解説する記事です。
文字のスタイル、レイアウト、形状が相互に依存していることや、テキストが個々の文字ではないことなどを説明しています。
アンチエイリアシングやフォントに関する問題点にも触れています。
-
-
-
Janet Jacksonの曲「Rhythm Nation」のPVが、PCをクラッシュさせる問題を発見。
原因は、曲に含まれる特定の周波数が、ノートPCのHDDの共振周波数と一致。
メーカーは、オーディオパイプラインにカスタムフィルターを追加し、問題の周波数を検出し除去することで対応。
-
-
-
自社開発企業から高年収オファーを得るためのノウハウを紹介。
規模の大きい開発経験や主体的なデリバリー経験が重要だと述べています。
プロダクト指向のマインドセットや技術力も不可欠であると解説。
-
-
-
2025年の増田文学300を紹介するWebコンテンツです。
匿名ダイアリーの記事がまとめられています。
様々なジャンルの投稿を読むことができます。
-
-
-
この記事は、AIが提案する個人別のホテル料金に関するものです。
ニューヨーク州がこの価格設定を規制する動きについて報じています。
特にMac利用者に対する料金が高い可能性があることを指摘しています。
-
-
-
GitHub Copilot ChatのAsk/Edit/Agentモードの違いをコードレベルで解説しています。
各モードはインテントと呼ばれるタスク実行の最小単位で動作します。
プロンプト、ツール、実行ループの違いから、各モードの設計思想を明らかにします。
-
-
-
T-Rubyは、Rubyに静的型付けを導入するプロジェクトです。
これにより、Rubyコードの信頼性と保守性を向上させることが期待できます。
サンプルコードでは、引数と戻り値の型を指定したメソッド定義が示されています。
-
-
-
正規表現の記法を忘れた時に便利な「ビジュアル正規表現エディタ」が紹介されています。
ブロックを組み合わせて正規表現を作成できるため、視覚的に理解しやすいです。
正規表現のテストエリアも用意されており、動作確認も可能です。
-
-
-
Manus AIのCSOであるPeak氏が、コンテキストエンジニアリングに注力した背景と教訓を解説。
モデルを自前で訓練するのではなく、文脈内学習能力を基盤としたエージェント構築のアプローチを紹介。
開発速度を向上させ、AI進化の波に乗るための具体的な方法を解説。
-
-
-
サイバーエージェントのデザインシステムSpindleの2025年の取り組みを紹介。
AIが開発の全工程に関与し、Spindle MCPサーバーの開発やDesign to Codeの実験を実施。
リポジトリ整備により開発速度が向上し、人とAIの共通言語としてのデザインシステムの重要性を強調。
-
-
-
語学サービス企業が1on1にAIを活用した事例を紹介。
AIが1on1の準備をサポートし、工数削減と質の向上を実現。
メンバーの成長支援とエンゲージメント向上に貢献している。
-
-
-
RustでProtobufを使った開発をする方法を検証した備忘録です。
Buf CLI、Connect Protocol、BSRなどのBufエコシステムを活用した開発について解説します。
tonicを使ったgRPCサーバーの実装や、protocheckを使ったバリデーションの実装例を紹介します。
-
-
-
GmailのGmailifyとPOP3サポートが2026年1月に終了し、他社メールの受信に影響が出る可能性が。
この記事では、影響を受けるかどうかの確認方法と、メールの一元管理を続けるための代替案を解説。
自動転送の設定やOutlookアプリへの移行など、具体的な対策を紹介。
-
-
-
HTMLとCSSのみでリバーシゲームを実装した記事です。
JavaScriptを一切使わずに、CSSの機能をフル活用しています。
counter-resetやposition/view()アニメーションの活用がポイントです。
-
-
-
Rustで書いたのにAPIのレスポンスが遅い原因を解説しています。
N+1クエリ問題の本質とRustとPostgreSQLを使った5つの解決策を紹介。
JOIN、IN句 + HashMap、array_aggなど、状況に応じた解決策を提示します。
-
-
-
Obsidianで研究ノートを管理する方法を紹介した記事です。
Obsidianのテンプレートを利用して、研究ノートの作成を効率化します。
ダッシュボードや実験ノート、論文ノートのテンプレート作成について解説しています。
-
-
-
2025年にProxmoxへの移行機会が増えた個人的な話です。
VMwareからの移行を検討している方の参考になることを願っています。
Proxmoxの良い点、イマイチな点を理解した上で移行を始めています。
-
-
-
RustとPostgreSQLでWebサービスを構築する際の注意点について解説されています。
浮動小数点数の累積誤差による問題と、その具体的な場面を提示しています。
適切なデータ型の選択や、Rustでの対策、パフォーマンス比較などを紹介しています。
-
-
-
AIレビュアーを活用したレビュープロセスを紹介しています。
ローカルレビューからCIレビューまで、AIが開発をサポートします。
ドキュメント整備やエージェント作成など、AI活用のための準備も解説しています。
-
-
-
Visual Studio 2026でGitHub Copilotを使う際の注意点について解説。
Agent modeではソリューションエクスプローラーにあるファイルしか参照できない制限があります。
`.github/instructions/**/*.instructions.md`の命名規則でファイルを配置するとAIが参照可能です。
-
-
-
uvがpipより高速な理由を解説した記事です。
Rustで書かれているだけでなく、設計上の決断が重要です。
高速化を可能にした標準規格、uvがサポートしない機能、Rustを必要としない最適化について説明しています。
-
-
-
医師の娘と統計家の父がコーヒーを飲みながら研究について語り合うサイトです。
研究で生じる疑問や論文の数字について、統計の世界を広げていきます。
研究仮説、統計、因果、言語という順で臨床研究を描いています。
-
-
-
APIをMCPサーバーとして使うことの問題点を解説しています。
AIのコストが高くなる、AIの応答精度が悪くなるという実害を指摘。
対策として、ツール数の削減、説明の簡潔化、応答データの絞り込みを提案しています。
-
-
-
陽子内部の複雑さについて解説。
陽子はクォークという素粒子で構成されていますが、その構造は非常に複雑です。
実験によって陽子の様々な側面が明らかになりつつあります。
-
-
-
成果を公開することが運を呼び込むというテーマの記事。
自分の得意なことや興味のあることを公開することで、より多くの人に知ってもらうことが重要だと説明し。
積極的に情報を発信することで、予想外の幸運が舞い込む可能性が高まることを示唆。
-
-
-
Windows歴7年のユーザーがArch Linuxに乗り換えた理由が書かれています。
Windowsの不安定さやAIのゴリ押し、macOSの自由度のなさなどが理由として挙げられています。
Arch LinuxのPacmanとAURの優秀さ、カスタマイズ性などが魅力として語られています。
-
-
-
ObsidianというMarkdownエディタを実際に使用した感想がまとめられています。
普段の作業との相性や、モバイル同期、Gitでの管理など、様々な側面からObsidianの使いやすさを評価しています。
最終的に、ObsidianとNotionを目的に応じて使い分けるのが良いという結論に。
-
-
-
RAGの仕組みを理解するために、手作りのRAGシステムを構築。
便利なマネージドサービスはあえて利用せず、RAGを構成する要素や、高品質な結果を得るための工夫を学びます。
LLMと埋め込みモデルの進化により、現代的なRAG戦略がどのように変化しているかを解説。
-
-
-
エンジニアの生産性を支えるdotfilesについて、その変遷と今年整備したconfigを紹介。
素朴なdotfilesからchezmoi、GNU Stow等の管理ツール、Home Managerまで解説。
momeemt/configのディレクトリ構成、Nixの設定、エディタ、ターミナル、Kubernetesまで詳細に解説し。
-
-
-
ソフトウェアエンジニアが面接で尋ねるべき質問について解説されています。
企業の文化や開発プロセス、技術的な課題を見抜くための質問が紹介されています。
給与だけでなく、働きがいのある環境かを見極める重要性が強調されています。
-
-
-
1995年にNetscapeの従業員が10日間で作成したJavaScriptは、現在インターネット上で使用されています。
当初はWebページをインタラクティブにするための軽量なスクリプト言語として開発。
その後、JavaScriptはWeb開発において不可欠な存在となりました。
-
-
-
Rob PikeがAIによって生成された感謝のメールを受け取り、激怒したという記事です。
AI Villageというプロジェクトが、AIエージェントに「親切な行為」をさせる実験の一環で送信されたものです。
著者は、AIが人々の時間を無駄にすることに警鐘を鳴らしています。
-
-
-
witrは、システム上で何かが実行されている原因を特定するツールです。
プロセス、サービス、ポートなど、実行中のものの背後にある原因を明確にします。
デバッグや障害発生時の理解を迅速化し、設定なしで動作します。
-
-
-
QNX Developer Desktopの初期リリース版が公開されました。
QNX 8.0上で動作するデスクトップ環境で、クロスコンパイルが不要になります。
QEMUイメージとして提供され、Linuxアプリケーションの移植が容易になります。
-
-
-
Firecracker microVMで構築された、自己ホスト可能なコード実行サンドボックスプラットフォームです。
安全かつ高速に、信頼されていないAIコードを実行できます。
スナップショットベースのウォームプーリングにより、200ミリ秒未満の起動時間を実現します。
-
-
-
ユタ自然史博物館の記事で、幻覚を引き起こす新しいキノコについて解説しています。
このキノコは学名Lanmaoa asiaticaといい、食べると小人の幻覚を見るという報告があります。
パプアニューギニア、中国、フィリピンなど、異なる地域で同様の報告があるのが興味深いです。
-
-
-
NVIDIA Tensor CoreユニットをターゲットにしたCUDAカーネル最適化のためのMLIRベースの中間表現とコンパイラ基盤です。
タイルベースの計算パターンと最適化に焦点を当てています。
高性能CUDAカーネルの開発を簡素化します。
-
-
-
SSHキーの盗難や悪用を防ぐためのセキュリティ対策について解説されています。
ハードウェアキーによる認証を導入することで、マルウェアによる攻撃から保護できます。
macOSでのSecretiveの利用や、FIDO2セキュリティキーの活用方法が紹介されています。
-
-
-
.NET RuntimeのPath.RemoveSegmentsの最適化に関する記事です。
旧実装の問題点を指摘し、新しいO(N)アルゴリズムとSIMDによる高速化を提案しています。
性能比較の結果、旧実装と比較して大幅な高速化を達成しています。
-
-
-
Kaggleコンペで停滞を打破するヒントを紹介しています。
「人力で解く」「上位陣を分析する」など、スコアアップに繋がる6つのアプローチを解説。
コンペの壁にぶつかった時に現状を打破するヒントになることを願っています。
-
-
-
Pythonの統計的プロファイリングに関するドキュメントです。
プログラムの動作を把握するために、定期的にコールスタックのスナップショットを取得します。
関数の呼び出しと戻りを計測するのではなく、一定間隔でコールスタックを読み取ります。
-
-
-
JavaScriptでLinuxディストリビューションを構築するプロジェクトです。
CとJavaScriptを組み合わせて、libcに依存しないマイクロLinux環境を実現します。
QEMUでの実行も可能で、Linuxの基礎を学べます。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より