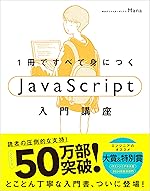-
-
ケント・ベック氏の講演録で、開発生産性の測定におけるグッドハートの法則の限界について議論。
指標管理がプレッシャーを伴うとシステムを破壊する可能性を指摘しています。
AI時代においては、コード量ではなく若手の学びを重視すべきだと述べています。
-
-
-
GoogleがコマンドラインAIツール「Gemini CLI」をリリースしました。
ちょっとした開発だけでなく、サーバーの運用アシスタントといった用途にも使えます。
AIアシスタントと外部のデータソースやツールを接続することを目的としています。
-
-
-
AIエージェント時代の知識創造企業について述べられています。
ソフトウェアエンジニアの仕事の変化と将来について考察されています。
AI時代に価値を生み出すための組織戦略と人材育成について解説されています。
-
-
-
Sansan Tech Blogの記事で、Agentic Codingについて紹介されています。
Agentic Codingとは、AIエージェントが自律的に計画を立て、コーディングを進めるスタイルのことです。
Claude Codeというツールを使い、実務でどのようにAgentic Codingを活用できるかを紹介しています。
-
-
-
セガ公式の「ぷよぷよプログラミング」ガイドブックが発売されます。
中高生向けのプログラミング入門書で、ゲームの作り方を解説し、最新版のソースコードを掲載しています。
開発環境はJavaScriptとMonaca Educationを使用し、ブラウザだけでゲーム作りが可能です。
-
-
-
グーグルが一部のPixel 6aに対してバッテリーパフォーマンスプログラムを開始します。
バッテリーが消耗したPixel 6aが対象で、無料交換を申し込めます。
ソフトウェアアップデートも提供され、バッテリーの容量と充電性能が調整されます。
-
-
-
夢日記のような不思議なタイトルの記事です。
内容は短編小説のようでもあります。
独特な世界観に浸りたいときにおすすめです。
-
-
-
三谷産業がAww Inc.と共同で「AI社外取締役」候補の北斗泰山を発表しました。
北斗泰山は孫子の知識体系をプリセットしたバーチャルヒューマンで、42歳(永遠の42歳)の東洋思想の専門家です。
法的要件を満たす取締役ではないものの、助言や提言を行うアドバイザーとして、盲点を発見する可能性が期待されています。
-
-
-
開発組織の進化とスケーリングにおける開発生産性について解説されています。
チームの状況によって開発生産性の意味や重要な指標が変化することを説明しています。
チームごとに意味のある生産性を定義し、改善していくことの重要性を説いています。
-
-
-
AIは励まされると頑張れるらしいという検証記事です。
様々な奨励方法でLPを作成させ、ビジュアル表現の変化を比較しています。
松岡修造風、プレッシャー型、ギャル語など、面白い試みが満載です。
-
-
-
AppleのSwift Core Teamが、SwiftでのAndroid公式サポートを目的とした「Android Workgroup」を発足しました。
これにより、Swift言語がAndroidを公式にサポートする方向性が明確になりました。
Android Workgroupでは、Swiftパッケージの強化やAndroid APIのサポート範囲の決定などが行われます。
-
-
-
Adobe Creative Cloudのプランが二分化され、生成AI機能が強化されたProとStandardが登場しました。
Proプランは生成AI機能が無制限で利用可能ですが、月額料金が引き上げられます。
Standardプランは生成AI機能が制限される代わりに、月額料金が抑えられています。
-
-
-
国産の高性能CSVエディター「SmoothCSV 3」が公開されました。
Windows/Macに対応し、フリーソフトとして利用可能です。
Excelのような直感的な操作性や、大きなファイルも扱えるパフォーマンスが特徴です。
-
-
-
この記事は、エンジニアが見積もり業務で直面する課題を解決するための知見を紹介しています。
見積もりの目的によってアプローチを変える、信頼性の期待値をコントロールする、チームで見積もることの重要性を解説しています。
見積もりを通じて、意思決定能力や全体を見通す力を養い、エンジニアとしての成長につなげられると述べています。
-
-
-
MCPサーバの作成手順を解説しています。
リソースとプロンプトを提供することで、Claude Desktopから利用可能になります。
Node.jsのインストールから、MCPサーバの構築、Claude Desktopでの動作確認までを網羅しています。
-
-
-
イーロン・マスクがTwitter(現X)を買収した理由について解説されています。
それは単なる気まぐれや道楽ではなく、彼がまだ手に入れていないものを得るためでした。
テクノ封建制の論理からマスクの真意を解き明かします。
-
-
-
東京都教育委員会が都立高校にDeepLを導入しました。
生徒と教員、計1万人以上が英語学習や業務支援に利用しています。
AIを活用し、教員の負担軽減と生徒の英語力向上を目指します。
-
-
-
JR東日本はJRE POINTのサービスを刷新し、キャンペーンを実施します。
2026年2月を目処に、モバイルSuicaアプリからJRE POINTの交換が可能になります。
JRE POINT10周年を記念して、10月にポイントが10倍になるキャンペーンも実施予定です。
-
-
-
AI時代において、情報過多で「何を言っているか」だけでは差別化が難しい時代になりました。
重要なのは、発信者の「信頼」であり、PdM(プロダクトマネージャー)はチームを巻き込むために「信頼」を築く必要があります。
日々の行動や関係性を通じて信用を積み上げ、共感や誠実さを示すことで「信頼」を得ることが重要です。
-
-
-
この記事では、Webサイトのパフォーマンス改善について解説しています。
mizchi氏がWeb Vitalsなどの指標を用いて、ボトルネックの特定から改善までのサイクルを解説します。
サーバーサイドだけでなく、ユーザー体験としての速度を重視する重要性を説いています。
-
-
-
Adobeがデジタル作品の来歴情報を埋め込む無料ツールACAを公開しました。
これにより、コンテンツの信頼性を担保し、無断転載や改ざんを防ぐことが期待されます。
画像に権利情報を埋め込み、AI学習への不使用意思表示も可能です。
-
-
-
Autifyが、仕様書を読み込ませることでテストケースを自動生成する「Autify Nexus」を発表しました。
自然言語で指示することでテストシナリオとテストコードを生成する機能も備えています。
仕様書がないコードから仕様書を作成する「Autify Genesis 2.0」も同時に発表されました。
-
-
-
この記事では、RubyでAIエージェントを実装する方法について解説しています。
AIエージェントの基本的な考え方や、動作原理を理解することができます。
ruby_llmライブラリを用いて、Claude 3 HaikuとCalculatorツールを組み合わせた簡単なAIエージェントの例を紹介しています。
-
-
-
AI技術を悪用したプロンプトインジェクション攻撃について解説されています。
特に、AIが処理する外部データに悪意のある指示を埋め込む間接的な手法に焦点を当てています。
偽のエラーメッセージを表示させ、ユーザーをフィッシングサイトへ誘導する手口を紹介しています。
-
-
-
この記事は、マイクロソフトが組織をフラット化していることについて解説しています。
6000人レイオフの裏側に何があるのかを考察しています。
社員が目の当たりにした変化について語られています。
-
-
-
iOS 26のFaceTimeに関する記事です。
服を脱ぎ始めると通話が停止するという仕様について解説されています。
詳細はGIGAZINEの記事をご覧ください。
-
-
-
gmailtailは、GmailメッセージをJSON形式で監視するコマンドラインツールです。
自動化、監視、他のツールとの連携を目的として設計されています。
リアルタイム監視、柔軟なフィルタリング、チェックポイント機能などを備えています。
-
-
-
Adobe Creative Cloudのプラン変更に関する情報が公開されました。
コンプリートプランがProプランに名称変更され、Standardプランが新たに登場します。
Standardプランは一部機能が制限されるものの、価格が抑えられています。
-
-
-
この記事では、Claude Codeを活用したスライド作成の効率化について紹介されています。
MarpとClaude Codeを組み合わせることで、会社テンプレートに沿ったスライドを自動生成する仕組みを構築しています。
移動中などの隙間時間にもスライド作成が可能になり、Zenn記事からLTスライドを生成する錬金術も紹介されています。
-
-
-
RhodoniteというWeb3Dライブラリの紹介記事です。
著者はRISV-VやOS開発にも興味があるとのこと。
多趣味な開発者によるTypeGPUの入門書です。
-
-
-
AIコーディングアシスタントによる危険なコマンド実行を防ぐための設定方法を紹介します。
Claude Codeのパーミッション機能を使い、rm -rfなどの危険なコマンドを禁止します。
settings.jsonを設定することで、AIの暴走からシステムを守ります。
-
-
-
ClaudeCodeで日本語入力をする際の不具合とその解決策について解説されています。
外部ファイルに指示を記述し、それを参照することで問題を回避します。
gitignoreの設定やカスタムスラッシュコマンドの活用など、試行錯誤の過程が詳細に記述されています。
-
-
-
この記事は、Claudeの会話再開コマンド`claude --resume`を使いやすくするCLIツール「ccresume」を紹介しています。
ccresumeは、過去の会話履歴を一覧表示し、詳細プレビューや即時再開、セッションIDのコピーが可能です。
React Inkを使用して開発されたCUIツールで、npxで簡単に実行できます。
-
-
-
FirestoreからCloud Spannerへの移行プロジェクトの記録。
40以上のコレクションを無停止で移行し、DBコストを93%削減。
クリーンアーキテクチャ、段階的移行、E2Eテストが成功の鍵。
-
-
-
tmuxをCからRustに移植したプロジェクト「tmux-rs」の紹介記事です。
C2Rustを使った初期の試みから、手動での翻訳に移行した経緯、そして直面した興味深いバグについて解説しています。
最終的にはyaccからlalrpopへの移行を経て、ビルドプロセスを最適化し、100% Rustでの実装に成功しました。
-
-
-
ケビン・ケリーは特定の「大きなこと」で知られているわけではありません。
彼は歴史的な起業家のように知的で勤勉で野心的ですが、ユニコーン企業を自分で作ることに興味がありません。
代わりに、彼は「ハリウッドスタイル」で創造的なプロジェクトに取り組んでいます。
-
-
-
この記事では、キャッシュを最適化ではなく抽象化として捉える考え方を解説しています。
キャッシュは、データアクセスを高速化するだけでなく、ソフトウェアをよりシンプルにするためのツールであると述べています。
異なるストレージ階層の概念を抽象化し、データ管理を容易にする役割を強調しています。
-
-
-
Wind Knitting Factoryは、風を利用してニット製品を製造するプロセスを紹介しています。
建物のファサードからニットが編み出され、窓を通して内部に運ばれます。
完成したスカーフには、風がスカーフを作った日時が記載されたラベルが付けられます。
-
-
-
Googleが年齢認証のためのゼロ知識証明(ZKP)ライブラリをオープンソース化しました。
プライバシー保護を強化し、安全な年齢認証技術の普及を促進します。
開発者はこの技術を利用して、個人情報を開示せずに年齢確認を行うことができます。
-
-
-
本棚の整理アルゴリズムに関する研究を紹介しています。
データの挿入時に本を移動させるコストを削減する新しいアルゴリズムが登場しました。
このアルゴリズムは、データ構造の分野に革新をもたらす可能性があります。
-
-
-
Hibikiという同時音声翻訳モデルが発表されました。
このモデルは、ソースとターゲットの音声を同時に処理し、テキストと音声トークンを生成します。
リアルタイムでの翻訳を可能にするため、遅延を最適化する弱教師あり学習法を導入しています。
-
-
-
この記事では、アメリカの都市におけるレストランの統計的分布を分析しています。
Google Places APIを利用して、都市の人口とレストランの種類の関係を調査しています。
統計的にありえないレストランの存在や、都市ごとの料理の偏りを明らかにしています。
-
-
-
1962年にNASAは人工重力を生成する回転ホイール宇宙ステーションの設計案を持っていました。
アポロ計画がそれを中止させましたが、もし人工重力の追求を続けていれば、深宇宙ミッションを支援する軌道上の居住地ができていたかもしれません。
商業宇宙企業が再び人工重力を検討しており、人類の宇宙進出における高コストな迂回路を修正する可能性があります。
-
-
-
Jake Gyllenhaalをインターネット上の100万個のチェックボックスにエンコードした方法について解説されています。
友人がチェックボックスの画像を見せたことがきっかけで、隠されたキャンバスにアニメーションのジェイクを描くことになりました。
当初は乗り気でなかったものの、最終的には1秒あたり5500回のフリップという驚異的な速度でアニメーションを実現しました。
-
-
-
Nature Chemistryに掲載された分子に関する記事です。
環状構造を持つ分子について解説しています。
化学に興味のある方はぜひご覧ください。
-
-
-
この記事では、D&D 5eにおける「農民レールガン」という戦術について解説しています。
2280人の農民を並べて棒を高速で伝達し、莫大なダメージを与えるという奇想天外な理論です。
現実的な問題点も指摘しつつ、DMが許可するかどうかについても考察しています。
-
-
-
AI4Researchという論文の紹介です。
科学研究における人工知能の利用に関する調査を行っています。
様々な分野でのAIの応用について議論しています。
-
-
-
AI業界におけるムーアの法則は終焉を迎えたのかもしれません。
GoogleのGemini Flashの値上げは、その警鐘となる可能性があります。
この記事では、LLMの価格設定の仕組みと、AI構築への影響を解説します。
-
-
-
Fei-Fei Li氏による、AIにおける空間知能の重要性に関する講演動画です。
YouTubeで公開されています。
AIの新たなフロンティアについて議論されています。
-
-
-
PennybaseはFirebase/Supabase/PocketbaseのようなBaaSをGoで実装したものです。
1000行以下のコードで、ファイルベースストレージ、REST API、認証、RBAC、リアルタイム更新などの機能を提供します。
CSVファイルによるデータ保存、スキーマ定義、ユーザー管理、アクセス制御などの仕組みを備えています。
-
-
-
この記事では、MCP(Model Context Protocol)の限界と、コード生成の利点について論じています。
MCPは推論に依存しすぎているため、特に大規模な自動化には適さないと著者は考えています。
代わりに、LLMを使ってコードを生成し、そのコードを検証するアプローチを推奨しています。
-
-
-
アリスの挿絵が可愛らしい、微分可能プログラミングの入門書です。
この書籍は、アリスのように、奇妙な微分可能ワンダーランドに足を踏み入れたばかりの人のために、この魅力的な分野への入門書として構想されました。
自動微分による関数の最適化の基礎から最先端のモデルまで、読者を導きます。
-
-
-
Homebrew HNは、Hacker Newsの情報を手軽にチェックできるWebサイトです。
新着記事や注目の記事を一覧で確認できます。
ITエンジニアや情報収集に関心のある方におすすめです。
-
-
-
この記事では、AI評価に関するよくある質問とその回答がまとめられています。
RAG(Retrieval-Augmented Generation)の定義や、LLMの評価方法、そしてエラー分析の重要性について解説します。
CI/CDと本番環境での評価の違いについても触れられています。
-
-
-
天文学者が、太陽系外から来た3番目の恒星間天体3I/ATLASを発見しました。
この天体は彗星の可能性が高く、これまでに発見されたどの恒星間天体よりも高速です。
3I/ATLASは秒速60kmで太陽に向かっており、今後の観測で詳細が明らかになるでしょう。
-
-
-
Netflix Tech Blogの記事で、AV1コーデックのFilm Grain Synthesis (FGS)技術について解説されています。
FGSは、フィルムの粒子感を再現し、視覚的な品質を向上させながらデータ効率を最適化します。
AV1 FGSを大規模に活用することで、ビットレートを削減しつつ、高画質のストリーミング体験を提供します。
-
-
-
ViscaCamLinkは、VISCAプロトコルを使用してネットワーク経由で接続されたPTZカメラのコントローラーです。
プリセットやホットキー、自由な方向への移動、ズーム速度の調整などの機能があります。
.NET 6が必要で、初回起動時にはカメラのIPアドレスとポートを入力する必要があります。
-
-
-
この記事では、XORの特性を利用したいくつかのプログラミング問題を解説しています。
欠損した数値の発見、インプレースな値の交換、重複した数値の発見といった問題にXORがどのように適用できるかを示しています。
特に、複数の欠損値や重複値が存在する場合の解決策についても議論されています。
-
-
-
クリーブランドに停泊した船で、科学者たちが未知の生命体を発見しました。
船の舵柱からタール状の物質が染み出ており、調査の結果、新種の単細胞生物である可能性が浮上しました。
この発見は、生命がユニークな場所に存在することを示唆しており、さらなる研究が期待されています。
-
-
-
Postcardがオープンソースとして公開されました。
これは個人ウェブサイトとニュースレターの機能を持つアプリケーションです。
カスタマイズ可能なシンプルなRuby on Railsアプリケーションとして提供されます。
-
-
-
この記事は、AIのコンテキスト管理について解説しています。
AIが文脈を理解し、適切に応答するための技術を紹介しています。
具体的な手法や応用例を通じて、AIの可能性を広げています。
-
-
-
OpenStreetMapの.osm.pbfファイルをSQLiteデータベースに読み込むシンプルなコマンドラインツールです。
データベースにデータを読み込んだり、R*Treeインデックスやアドレステーブルを追加したりできます。
GeofabrikなどのプロバイダーからOSMデータを取得できます。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より