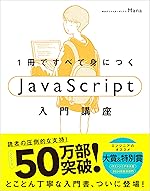-
-
この記事では、著者のキャリアに影響を与えたコンピューター・ITの定番書籍が紹介されています。
Webアプリケーション、ネットワーク、データベース、ソフトウェア設計など、分野別に書籍が分類されています。
各書籍の簡単な紹介と、なぜそれらが重要なのかがまとめられています。
-
-
-
LinuxのTuxくんやGoのGo Gopherくんなど、IT界隈で動物がロゴやマスコットとして採用されることはよくあります。
この記事では、IT界隈でよく見る動物たちの名前や由来を調べています。
架空の生物であっても、動物っぽいものであれば記事にしています。
-
-
-
この記事では、iPhoneのホーム画面を1画面に整理する運用方法を紹介しています。
アプリの整理方法やDockの活用、ウィジェットの選び方など、具体的な手順が解説されています。
1画面運用によって、アプリを探す時間の削減や集中力UPなどの効果が得られるとしています。
-
-
-
ObsidianとClaudeを活用したコード管理術を紹介。
効率的な情報整理とAIによるサポートで開発を加速。
Docswellで詳細な資料が公開されています。
-
-
-
AIの最新技術をまとめた記事です。
Kimi K2、MemOS、4KAgent、WebSailorなどが紹介されています。
AI技術の進歩が目覚ましいことがわかります。
-
-
-
メールアドレス認証の2FAは、パスワードが漏洩した場合に突破される危険性があります。
多くのSNSでは、パスワードだけでメールアドレス変更が可能なため、ハッカーに乗っ取りの隙を与えます。
対策として、メールアドレス以外の2FA要素を設定し、パスワードの定期的な変更を推奨します。
-
-
-
グーグルがGmailの新機能「シールドメール」を開発中です。
これは、オンラインでメールアドレス入力を求められた際に、本来のアドレスの代わりにエイリアスを生成できる機能です。
不要になったエイリアスは削除でき、スパム対策に有効です。
-
-
-
この記事では、牛尾 剛氏がプロダクションコードでVibe Codingをどのように活用しているかを紹介しています。
GitHub Copilot Agentなどのツールを使い、自然言語で指示してプログラムを生成する方法について、具体的な手順と注意点を解説しています。
特に、ディープコードリーディングによる理解の深化、AskモードでのAgentとの設計相談、そして実装という流れを重視しています。
-
-
-
この記事では、主要なオープンモデルを定義するアーキテクチャの進化に焦点を当てています。
DeepSeek V3、OLMo 2、Gemma 3など、最新のLLMアーキテクチャを比較検討しています。
各モデルの設計上の選択、特に正規化層の配置や注意メカニズムについて詳しく解説します。
-
-
-
GoogleのAI「Gemini」のカスタムGem応用編です。
アプリ連携やファイル活用で、あなただけのGeminiをさらに進化させられます。
記事では、実践的で高度なカスタムGemの作り方を紹介しています。
-
-
-
iPhone17 Proにマジョーラカラーがラインナップされるかもしれないという情報です。
光の当たり具合で色が変化する特殊なペイントが採用される可能性について解説しています。
ただし、色の変化具合に個体差が出る可能性があり、Appleが採用するかは疑問視されています。
-
-
-
AWS MCP Serversは、LLMアプリケーションと外部データソースやツールを統合するオープンプロトコルであるMCPを利用します。
AWSのドキュメント、ガイダンス、ベストプラクティスへのアクセスをAIアプリケーションに提供します。
クラウドネイティブ開発、インフラ管理、開発ワークフローを支援し、AI支援によるクラウドコンピューティングを効率化します。
-
-
-
AWS Summit NYC 2025のキーノートから、AWSがAIエージェント開発を実用レベルに進化させたことがわかります。
Amazon Bedrock AgentCoreの発表により、AIエージェントはデモだけでなく本番環境でも活用できるようになりました。
AgentCoreは、実行環境、記憶システム、セキュリティ、Web操作の自動化など、AIエージェントに必要な7つのコンポーネントを提供します。
-
-
-
寝ている間に雨が降り、朝起きたら庭が大変なことに。
水没した庭の様子がまとめられています。
「最悪」「衝撃的」といったコメントが寄せられています。
-
-
-
個人のプログラミング体制の現在地について書かれています。
最近の道具として、LLMエージェント、CI環境、タスク管理ツールなどを紹介しています。
個人の開発フォーメーションであり、所属先の業務体制ではないと述べています。
-
-
-
イーロン・マスクのAI「Grok」にアニメ風のコンパニオン機能が追加されました。
AIとの対話は依存や誤情報の危険性があり、倫理的な懸念があります。
AIが目指すべき方向性やインターネットの未来に疑問を投げかける内容です。
-
-
-
芥川賞作家の九段理江さんが、AIとの共作について語っています。
AIを戦略的に使おうとしたわけではなく、言葉へのこだわりが強いそうです。
翻訳では意味よりもリズムを重視しているとのことです。
-
-
-
エムスリーのSREエンジニアが、Gemini CLIを使ってサーバ運用を効率化する試みを紹介しています。
メールサーバのログ分析や設定変更作業をAIと対話しながら行い、その効果と課題を検証しています。
Linuxサーバ運用における生成AIの可能性と限界、今後の活用に向けた展望を述べています。
-
-
-
この記事は、BunとTypescriptを使用して10億行のファイルを10秒未満で解析する方法について解説します。
ファイルI/O、チャンク戦略、CPUのワークロードについて掘り下げています。
最終的な解決策はGitHubリポジトリで公開されています。
-
-
-
この記事では、GoでCLIを開発しOSSとして公開する際に、依存するライブラリなどのライセンス文書を一緒に配布する方法を紹介しています。
go-licensesというツールを使うことで、ライセンスのチェック、リストの出力、ライセンス文書の出力が可能です。
GoReleaserと組み合わせることで、リリース時にライセンス文書をバイナリと一緒に配布できます。
-
-
-
米AstronomerのCEOが辞任しました。
コールドプレイのライブで同僚との親密な様子が撮影され、SNSで拡散されたことが原因です。
同社はAI関連のクラウドプラットフォームを手掛けています。
-
-
-
パナソニックが欧州市場向けに4G対応フィーチャーフォン「KX-TF400」を発売します。
通話やメッセージに特化し、最大8日間の待ち受けが可能です。
日本での販売は未定ですが、SIMフリーケータイとしての需要が見込まれます。
-
-
-
生成AIの真の使い所は作業コスト削減ではなく、意思決定コスト削減にあるという主張の記事です。
組織の情報を集約し、生成AIで解析することで、中間管理職の役割を代替できる可能性について解説しています。
AIネイティブな組織への移行と、それによる効率化について考察しています。
-
-
-
GIGAZINEで紹介されたオープンソースの4本指ロボットハンド「Amazing Hand」に関する記事です。
低コストで製作可能であり、DIYや研究用途に活用できます。
ロボット工学に興味がある人にとって魅力的な情報源となるでしょう。
-
-
-
人とくるまのテクノロジー展2025名古屋の参加記録です。
勉強会や展示会の様子が詳細に記述されています。
自動車技術に関する最新動向を知ることができます。
-
-
-
この記事では、クラウドの日本語TTS(テキスト読み上げ)サービスを比較検討しています。
Gemini、OpenAI、Azure、にじボイスの応答性能と精度(人っぽさ)を比較しています。
主観評価では、にじボイスが最も自然だが高価、Azureは応答速度が速いがロボット感が強いと結論付けています。
-
-
-
AWSのAIエディタKiroのAgent Steeringについて解説されています。
仕様駆動開発を支えるAgent Steeringの仕組みが良いと筆者は述べています。
コンテキストの分割管理や適用範囲の柔軟性などがメリットとして挙げられています。
-
-
-
脆弱性調査に関する記事です。
調査で見つけた脆弱性について解説されています。
具体的な事例を通してセキュリティの重要性を伝えています。
-
-
-
オープンソースのセキュリティアラート管理プラットフォーム`Warren`についての記事です。
`Warren`はAIによる高度な分析とチームによる効率的なインシデント対応を支援します。
多様なソースからアラートを集約し、Slackとの連携でチームの協調的なインシデント対応をサポートします。
-
-
-
XMLUIは、ReactコンポーネントをXMLマークアップで構成し、Webアプリケーション開発を容易にする技術です。
Visual Basicのように、専門的なコーディングスキルがなくてもUIを構築できます。
テーマやリアクティブなデータバインディングもサポートし、AIとの連携も強化されています。
-
-
-
この記事では、レーザーを使って新しい色を作り出す研究を紹介しています。
また、目の錯覚を利用して、通常では見ることができない色を体験できる可能性について考察しています。
記事の後半では、読者が自分で錯覚を作り出すツールを提供し、様々な色の組み合わせを試すことを勧めています。
-
-
-
OpenBSDのstdio(3)のFILE型がopaqueに変更されました。
これにより、libcや関連ライブラリのバージョンが上がりました。
ソースからビルドするユーザーは、スナップショットアップグレードを強く推奨されています。
-
-
-
この記事では、SVGフィルターを使用して手描きのカートゥーンアニメーションでよく見られる「沸騰」効果をシミュレートする方法を紹介しています。
ノイズテクスチャを生成するTurbulence Fieldと、それを使用して画像を歪ませるDisplacement Mapを組み合わせて使用します。
JavaScriptでフィルターのパラメーターをアニメーション化することで、静止画像に動きのある手描き風の印象を与えることができます。
-
-
-
Gemini 2.5 PROなどのLLMはプログラマーの能力を拡張し、増幅します。
問題を明確に記述し、LLMとのやり取りを受け入れることができれば、信じられないほどの成果を上げられます。
人間の指示と監督の下でLLMを使用することで、高品質なコードを作成し、自身の知識と専門性の範囲を広げることができます。
-
-
-
FFmpegの開発者が、手書きアセンブリコードによって大幅なパフォーマンス向上を達成したと発表しました。
特定の関数において、AVX512をサポートする環境で最大100倍の速度向上を実現しています。
コンパイラでは難しい最適化が、手書きアセンブリによって可能になった事例です。
-
-
-
著者はポーランドからの移民の娘であり、母親との思い出を振り返っています。
母親は過去の苦難を語らず、アメリカでの生活を重視していました。
しかし、晩年にはポーランドを離れたことを後悔する言葉も漏らしていました。
-
-
-
Peep Showは、ロンドンに住む2人のルームメイトの日常を描いたイギリスのテレビドラマです。
主人公たちはエゴイスティックで自己中心的で、周りの人々を巻き込みながら様々な問題を引き起こします。
本記事では、彼らの行動を通して「悪」とは何かを考察し、私たちが学ぶべき教訓を提示します。
-
-
-
ZSHシェルの起動速度を改善する方法を紹介しています。
zprofを使ってボトルネックを特定し、Oh-My-Zshの自動アップデートを無効化、completionのキャッシュ、Spaceship promptの最適化などを行っています。
最終的に、起動時間を大幅に短縮することに成功しています。
-
-
-
Subreplyは、小さくても強力なソーシャルネットワークです。
https://subreply.comでアカウントを作成できます。
インストールや起動方法が記載されています。
-
-
-
Teufel初のオープンソーススピーカー「MYND」の開発秘話が語られています。
工業デザイナーと電気エンジニアが、その耐久性とカスタマイズ性について語っています。
持続可能性を重視し、修理の容易さや素材の選択にこだわった設計思想が特徴です。
-
-
-
この記事では、iFrameを使用してダッシュボードを埋め込むことのデメリットについて解説しています。
iFrameを使用すると、デザインの一貫性が損なわれたり、フロントエンドとの連携が制限されたりする問題が発生します。
セキュリティリスクやパフォーマンスの低下も考慮し、より良い代替手段としてEmbeddableを紹介しています。
-
-
-
フランス政府の米国ハイテク企業への依存が、デジタル主権に関する懸念を高めています。
上院報告書は、重要なデータインフラを米国の法律に従う米国企業に委託することを「政治的過ち」と非難しています。
これにより、医療、教育などの公共データが米国の監視にさらされると警告しています。
-
-
-
この記事では、大規模言語モデル(LLM)のアーキテクチャの比較について解説します。
DeepSeek V3、OLMo 2、Gemma 3など、様々なモデルの構造的な違いに焦点を当てています。
特に、注意機構、正規化層、MoE(Mixture-of-Experts)などの要素に注目し、各モデルの設計選択を探ります。
-
-
-
Tonieboxという子供向けの音楽プレイヤーのハッキングに関する記事です。
NFCタグを利用した仕組みや、クラウド連携によるトラッキングの問題点について解説されています。
SDカードからのバックアップやカスタムファームウェアの導入など、様々なハック事例が紹介されています。
-
-
-
JOVEは、カリフォルニア大学サンディエゴ校で開発された教育用オペレーティングシステムです。
Pascalで記述されており、PDP-11上で動作しました。
教育目的で設計され、オペレーティングシステムの概念を学ぶために使用されました。
-
-
-
MicrosoftのMac Labのツアーを紹介する、2006年の記事です。
MacBUが優れたソフトウェアを開発するために行っていることを解説しています。
多数のMacintoshと自動化システム、テスト環境について詳しく説明しています。
-
-
-
MacBookのノッチを有効活用するツール、QuakeNotchの紹介です。
Patreonでの支援も受け付けており、無料でダウンロードも可能です。
ライセンスキーを購入すると、メールでアクティベーションキーが送られます。
-
-
-
AIがウェブを脅かしているという内容の記事です。
CloudflareのCEOであるMatthew Prince氏がメディア企業の幹部から相談を受けました。
AIによる新たなオンラインの脅威について語られています。
-
-
-
「Caveman to Chemist」は、現代産業文明への道筋となった画期的な技術を探求するコースのWebサイトです。
火や石器の作り方から始まり、プラスチックや半導体へと進んでいきます。
化学の学習リソースとして最適です。
-
-
-
Linuxにおける非同期I/Oと永続性についての記事です。
io_uringを使用してWALを最適化し、データベースのパフォーマンスを向上させる方法を解説しています。
意図WALと完了WALの2つのWALを使用することで、一貫性を保ちつつ高いスループットを実現します。
-
-
-
この記事では、AI研究における「ビターレッスン」の誤解について議論しています。
データと計算を活用した汎用的な手法と、人間の知識は二項対立ではないと主張しています。
モデル構築の過程で、両者のバランスとトレードオフが必要であることを述べています。
-
-
-
オーストラリアで、YouTubeの視聴に年齢確認が義務付けられる可能性が出てきました。
きっかけは子供をSnapchatから遠ざける計画でしたが、対象はTikTok、そしてYouTubeへと拡大しています。
デジタルIDシステムの導入により、DIY動画や音楽、子供向け番組の視聴にも身分証明が必要となるかもしれません。
-
-
-
「民主主義そのものを危うくするセキュリティホールだ」とNieRシリーズのクリエイターであるヨコオタロウ氏が発言。
クレジットカード決済代行業者が日本の成人向けコンテンツプラットフォームに圧力をかけている問題について言及しています。
決済処理会社がコンテンツ配信のインフラ全体に関わることで、言論統制が可能になる危険性を示唆しています。
-
-
-
Minecraftの音楽が作曲家Daniel Rosenfeld氏にとって大きなビジネスになった経緯を紹介しています。
彼はゲームの成功を見越して音楽の権利を保持し、Microsoftへの売却を拒否しました。
その結果、彼の音楽は今もなおストリーミングやレコードで収益を上げ続けています。
-
-
-
1997年当時のJavaは非常に話題になっていた、という2021年の記事です。
当時、Javaは多くのハイレベル言語に導入された最初の主流言語でした。
しかし、JavaはWindowsデスクトップアプリの分野ではVisual BasicやVisual C++に劣っていました。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より