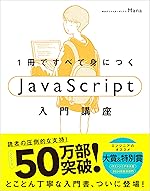-
-
モバイルSuica利用時の注意点をまとめた記事です。
機種変更時のデータ移行、バッテリー切れ、残高不足など、よくあるトラブルとその対策を紹介しています。
快適なモバイルSuica利用のために、設定や使い方を見直しましょう。
-
-
-
開発現場で役立つコミュニケーション方法論を解説した書籍の紹介記事です。
図の書き方、文章の伝え方、ドキュメント管理、リモートワークなど、多岐にわたる情報伝達術を体系的に学べます。
C4モデルや認知バイアス、パースペクティブ駆動ドキュメンテーションなど、具体的なTipsも紹介されています。
-
-
-
AWSインフラエンジニアが開発したCLIツールhawkの開発背景を紹介しています。
JSONやYAMLの構造把握を効率化し、pandas風の操作感でデータを扱えます。
Rust製で高速かつ軽量、学習コストが低いのが特徴です。
-
-
-
Dockerイメージの選び方について解説されています。
標準、Slim、Alpine、Scratchの各イメージの特徴と、どのような場合に選ぶべきかを説明しています。
用途、互換性、リソース制約を考慮した選択フローチャートも掲載されています。
-
-
-
LLMのAPIを活用したバックエンドアーキテクチャの事例を紹介する記事です。
YOJO事業部で使用しているバックエンドアプリケーション(Ruby on Rails)において、LLMのAPIをどのように取り扱っているのかをシステム構成の観点から解説します。
LLMの応答速度の遅さを考慮し、非同期処理、タスクの隔離、割り込み処理の考慮、バッチ処理のような扱いが必要であると述べています。
-
-
-
Windowsのライセンス形態は大きく分けて3種類あります。
OEMライセンス、リテールライセンス、ボリュームライセンスがあり、それぞれ適用対象や有効化方法が異なります。
ライセンス情報を確認するには、slmgr.vbsコマンドを使用できます。
-
-
-
2025年7月10日の「FRAIM×LayerX検索ミートアップ」での登壇資料。
イベントタイトルは「~LLM時代の検索~」。
COLIEE2025で発表した内容の紹介が中心です。
-
-
-
この記事では、AIによって失われる仕事がある一方で、新たに生まれる職業に焦点を当てています。
今後10年間で需要が高まるであろうAI関連の7つの職業を紹介しています。
AIが人間の仕事を変化させ、機械知能と人間の判断力を組み合わせた新しい働き方が求められると述べています。
-
-
-
この記事では、AIコーディング環境を構築するために試行錯誤した結果と教訓がまとめられています。
CursorとClaude Codeの組み合わせが最適であると結論付けています。
ツールの使い分けや契約プラン、長期契約の注意点など、実践的な情報が満載です。
-
-
-
Container Useは、AIコーディングエージェントにサンドボックス環境を提供するDagger開発のMCPサーバーです。
これにより、AIが実行するコマンドがユーザーのシステムに影響を与えずに実行できます。
この記事では、Container Useのインストールから利用、変更の適用までを解説します。
-
-
-
eBPFを活用してSREのスキルアップを目指すガイドです。
Speaker Deckで公開されており、具体的な活用ステップが解説されています。
phpのコンパイルに関するUSDTプローブの例も紹介されています。
-
-
-
この記事は、AppleがPasskeyを発表したことが、認証業界に大きなイノベーションをもたらしたと述べています。
Passkeyは、WebAuthnをベースにしながらも、秘密鍵をiCloud Keychainで同期するという掟破りな方法を採用しました。
これにより、パスワードに頼らず、より安全で使いやすい認証手段が実現したとしています。
-
-
-
このスライドは、AIエージェントにAWS CloudFormationを直接書かせることの是非について議論しています。
AWS CDKを使う必要性について疑問を投げかけています。
AIエージェントによるインフラ構築の可能性を探る内容です。
-
-
-
テレワークの利用率は全国で13%、東京圏で21%と、コロナ禍以前と大きな変化は見られません。
テレワークで仕事の効率性を維持できると考えている人は約16%に留まっています。
自然災害時にもテレワークを推奨しない企業が多いという実態が明らかになりました。
-
-
-
Claude CodeがWindowsをサポート開始したという速報です。
Windows環境での開発のやる気が復活するかもしれません。
ただし、まだリリースしたばかりでいくつかの不都合があるようです。
-
-
-
この資料は、グローバルサービスの信頼性向上戦略について解説しています。
SREが主導し、Amazon S3のクロスリージョンレプリケーションの改善に焦点を当てています。
アップロード速度の改善やS3バケット構成の簡素化など、具体的な対策を紹介しています。
-
-
-
この記事は、日本語セキュリティLLM開発の挑戦と挫折、そして発見について述べられています。
社内SE時代の経験から、AIでインシデント対応を民主化したいという思いが原点となっています。
日本語の学習データがないという課題に対し、日本語化された「ATT&CK × Kill Chain」データセットを作成する過程が詳細に解説されています。
-
-
-
WindowsでClaude Codeを利用する際、WSLが不要になったようです。
ローカルインストールで試した結果、Windowsで直接扱えるようになりました。
GitHubのリポジトリ情報も更新され、Windowsネイティブサポートが追加されています。
-
-
-
この記事では、中国人が日本の土地や不動産、水源を買いまくっているという噂について検証しています。
財務省のデータやCBREのデータをもとに、外国人が所有する日本の不動産の実態を分析しています。
結論として、中国による不動産買い占めはデマであり、水源地詐欺事件の真相を解説しています。
-
-
-
Claude Code UIは、AnthropicのAI支援コーディングツールClaude Codeの公式CLIを操作するためのデスクトップ・モバイルUIです。
ローカルまたはリモートで利用でき、プロジェクトやセッションの表示、変更が可能です。
直感的なインターフェースで、どこからでもClaude Codeを利用できます。
-
-
-
アップルがAI戦略で新たな動きを見せています。
画像生成AI市場でOpenAIやグーグルが競争する中、アップルは独自開発の「STARFlow」で差別化を図ります。
ChatGPTとの統合も一時的なもので、最終的には自社開発の画像生成システムに置き換える可能性があります。
-
-
-
Alpine Linux開発者が軽量“X on Wayland”コンポジタ「Wayback」をローンチしました。
Waylandセッション上でもXアプリをそのまま動かす互換レイヤとして提供されています。
レガシーなウィンドウマネージャやデスクトップをWayland上で再現を目指しています。
-
-
-
このブログ記事では、LLM Agentに意味のある単位でコミットさせる方法を紹介しています。
カスタムスラッシュコマンド`semantic_commit`を使い、git addを封印します。
これにより、レビューしやすい、revertしやすいコミットを実現します。
-
-
-
この記事では、AIを活用した自動運転のプログラミングについて解説しています。
AIコードエディタを使用し、ROS2パッケージ『Vibe Coding Kit』を設計、開発する過程を紹介しています。
OpenCVや深層学習(DeepLabV3)の導入、BEV変換など、様々な試行錯誤を通じて自動運転AIの課題と可能性を探っています。
-
-
-
MastraとOllamaでローカルAIエージェントを構築し、Tool Use時にストリーミングできない課題を解決しました。
ollama-ai-providerをフォークし、Tool Use時のストリーミングに対応させたnpmパッケージを公開しました。
AITuberKitとの接続も行い、ローカルAIエージェントの活用例を示しました。
-
-
-
この記事では、B200でNVFP4量子化モデルの推論を試した結果がまとめられています。
速度と精度の比較が行われ、FP8モデルとの違いが明らかにされています。
今後の最適化によりNVFP4がより優位になる可能性が示唆されています。
-
-
-
この記事では、Claude Codeを使用してLTスライドをHTML形式で作成する方法を解説しています。
SlidevやMarpなどの学習コストをかけずに、Web開発の知識を活かしてスライド作成が可能です。
mdファイル資産の活用やGitHubでの管理、CSSによる一括変更など、多くのメリットが紹介されています。
-
-
-
この記事では、ゲーム開発におけるAIコーディングの活用が遅れている現状について考察しています。
設計思想の明文化、ガードレールの重要性、コンテキストの構造化といったAI活用に必要な要素を提示しています。
今後のゲーム開発におけるAI活用のための文化づくりや具体的なツール開発の方向性を示唆しています。
-
-
-
この記事では、neoAIが開発した日本語Reasoning Modelについて解説しています。
継続事前学習とモデル重み差分の活用により、日本語能力と推論能力を効率的に統合しています。
ベンチマーク結果や出力例も紹介されており、日本語での思考過程が確認できます。
-
-
-
LaravelとNext.jsを用いたWebアプリケーション開発に関する書籍です。
TerraformとGithub Actionsを利用したAWS ECS Fargateへのデプロイ方法も解説されています。
SNSアプリ開発を通して、実践的なスキルを習得できます。
-
-
-
個人開発で複雑になりすぎた設計から、引き算の設計術を学んだ話。
Unityの強力な機能を使いすぎると、かえって変更やデバッグが難しくなる経験を紹介。
UIの自動化、データ形式の統一、保存データの絞り込みなど、具体的な改善策を解説します。
-
-
-
OpenCutは、Web、デスクトップ、モバイル向けの無料のオープンソース動画エディターです。
プライバシーが保護され、動画はデバイスに保存されます。
CapCutの基本的な機能はすべて無料で利用でき、シンプルで使いやすいエディターです。
-
-
-
ソフトウェア開発に関する記事です。
ピクセルや色、フォントやベクター画像、3Dとシェーダーなど、様々なトピックを解説。
技術者向けの詳しい情報が記載されています。
-
-
-
世界のフードデリバリー市場は、上位5社に90%以上を握られる寡占状態になりつつあります。
市場の寡占化は、顧客、配達員、レストランのそれぞれに影響を与えます。
投資の観点からは、フードデリバリー業界はまだ成長の可能性を秘めています。
-
-
-
Raycastに触発されたLinux用のオープンソースのランチャーです。
Raycastのコア機能をLinuxで再現することを目指しています。
拡張機能のサポート、強力な計算機、クリップボード履歴、スニペット、AI統合などの機能があります。
-
-
-
イランのインターネット遮断に関する技術的な分析について解説されています。
国内向けネットワーク(NIN)を構築し、国際的な接続を遮断しても国内サービスを維持できるようにしています。
IPアドレスの再割り当てやICMPトンネル、Starlinkなどを利用した検閲回避策も紹介されています。
-
-
-
APKLabは、VS Code内でAndroidアプリのリバースエンジニアリングを支援するツールです。
Quark-Engine, Apktool, JadxなどのOSSツールを統合し、IDEを離れることなくアプリ分析が可能です。
APKのデコード、Smali/Javaへの逆コンパイル、MITMパッチ適用、APKの再構築・署名・インストールなどの機能を提供します。
-
-
-
2025年に初めてウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』を読んだ感想が述べられています。
サイバーパンクの原点であり、その後のSF作品に多大な影響を与えた作品とのことです。
未来の技術予測の難しさや、SFが人間の状態を理解するための物語であることを語っています。
-
-
-
ゴットルプの地球儀は、350年前に天文学的な驚異として知られていました。
歴史上最初のプラネタリウムであり、フリードリヒ3世の国際性の代名詞です。
内部には最大12人が入ることができ、当時の夜空を見ることができました。
-
-
-
GLP-1受容体作動薬(GLP-1s)が生命保険業界に影響を与えていることについての記事です。
GLP-1sの使用者が保険加入時に健康状態を良く見せかけることで、保険会社がリスク評価を誤る可能性を指摘しています。
保険会社は質問方法の改善や、GLP-1s使用者のリスクプロファイルに安全バッファを追加するなどの対策を講じています。
-
-
-
北朝鮮の偽IT労働者の問題が深刻化しており、企業が対策を講じる必要性が高まっています。
多くの企業が偽の履歴書や面接でのなりすましに気づかず、セキュリティ侵害のリスクにさらされています。
企業は採用プロセスを見直し、身元確認を強化することで、この問題に対処できます。
-
-
-
この記事では、インターネット上での極端な意見や誤情報が、一部の活発なユーザーによって拡散されている現状を解説しています。
その結果、社会が実際よりも分断され、怒りに満ちているかのように感じてしまうと指摘しています。
健全な情報摂取のために、偏った意見を避け、バランスの取れた情報源を選ぶことを推奨しています。
-
-
-
C3言語におけるメモリ管理の新しいアプローチを紹介しています。
Tempアロケータという仕組みを導入し、メモリリークを防ぎつつ、パフォーマンスを向上させることを目指しています。
スコープに基づいてメモリのライフサイクルを管理し、自動的にクリーンアップすることで、手動管理の利点と安全性を両立させています。
-
-
-
TorchLeetはPyTorchと深層学習のスキルを向上させるための問題集です。
基礎から応用まで様々なレベルの問題が用意されています。
LLM(大規模言語モデル)を理解し、実装するための新しい問題も追加されました。
-
-
-
この記事では、大規模言語モデル(LLM)における強化学習(RL)のスケールアップについて議論されています。
現在のRLは計算コストが高く、検証可能なタスクに限定されているため、Webデータを用いた次トークン予測によるRLが提案されています。
このアプローチにより、LLMはWeb上の多様なデータから推論能力を獲得し、より効率的な学習が可能になると期待されます。
-
-
-
AxonのDraft Oneは、警察官のボディカメラの音声から警察報告書を作成するAI製品です。
EFFの調査によると、この製品は、公への説明責任を果たすための監査を意図的に回避するように設計されているようです。
AIが生成した部分と警察官が書いた部分を区別することが困難であり、透明性の欠如が懸念されています。
-
-
-
この記事では、強化学習(RL)におけるGPT-3のようなブレイクスルーの可能性について議論しています。
大規模な環境で学習させることで、汎用的な能力を獲得し、新しいタスクに迅速に適応できるモデルが生まれると予測しています。
そのために、既存のソフトウェア製品をAIに複製させる「replication training」という新しいパラダイムを提案しています。
-
-
-
ハンガリー最古の図書館が、10万冊の書籍を甲虫の被害から救おうと奮闘しています。
1000年以上の歴史を持つこの図書館は、ハンガリーの宗教的、文化的中心地です。
気候変動の影響で甲虫の発生が増加し、書籍の保存が困難になっています。
-
-
-
FreeBSDに関する情報を提供するチャットボットをローカル環境で構築する方法を紹介しています。
OllamaとOpen-WebUIをインストールし、FreeBSDのドキュメントを学習させることで、FreeBSDに特化した質問応答が可能になります。
技術的な質問に対して正確な回答を提供し、FreeBSDの利用、管理、開発を支援します。
-
-
-
このオンラインブックでは、Prompt Engineeringの基礎から応用までを学ぶことができます。
スタンフォードやMITなどの研究に基づいた信頼性の高い情報が満載です。
チャットボットから複雑な推論システムまで、8つ以上の実際のプロジェクトを通して実践的に学習できます。
-
-
-
グレアムのANSI Common Lispに関するノートです。
コードの保守性と移植性は高いですが、命名規則や条件分岐、ループ処理に特徴があります。
短い名前の使用、if文の多用、loopの回避などが挙げられます。
-
-
-
Homelab環境のモニタリング設定について書かれています。
独自のツールを使い、HTTP/DNSなどを定期的にチェックし、ntfy.sh経由で通知を受けます。
設定の容易さ、メンテナンス性、そして少ない可動部分に重点を置いています。
-
-
-
この記事では、LLMにおけるTool/Function Callingについて解説されています。
RESTとSpring AIでのステップバイステップの例が紹介されています。
Spring AIがどのようにツールスキーマ生成や引数バインディングを処理するかが説明されています。
-
About
「topickapp」は、個人運営の趣味と実益を兼ねたニュースサイトです。
インターネットに公開されているIT技術系のニュースを始めとして、セール情報、おもしろ情報、海外ニュースなども扱っています。
できるだけ毎日更新して、コンテンツを増やしていきます。
よろしくお願いいたします!
サイト管理人より